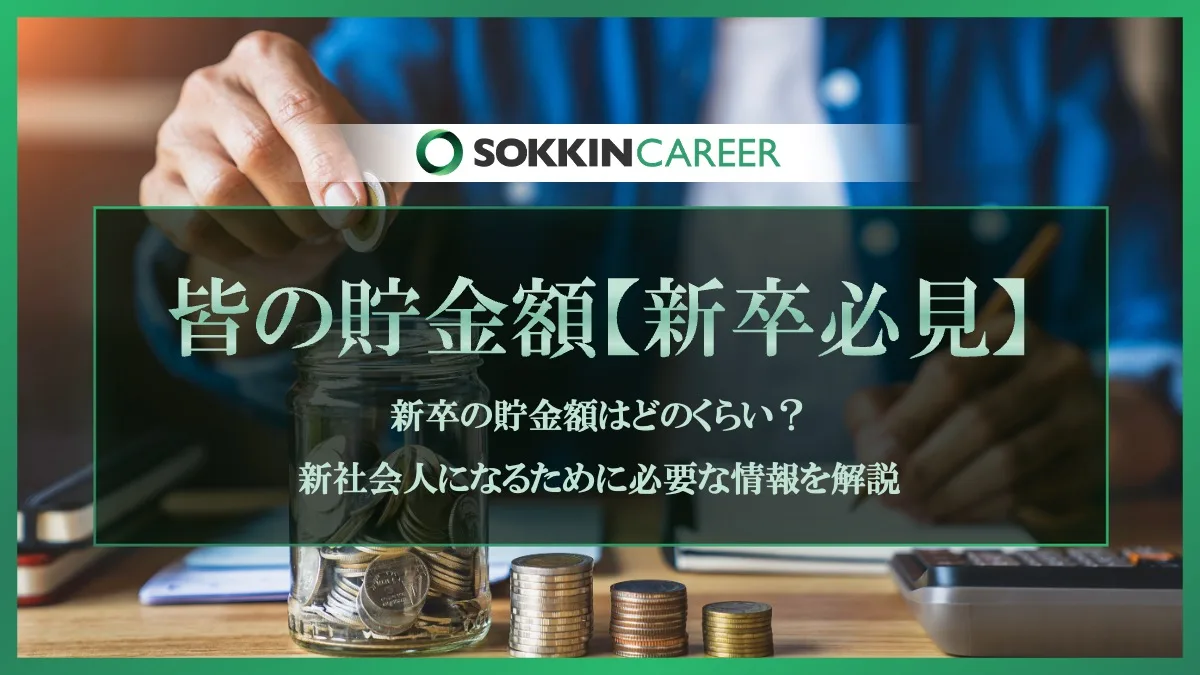新社会人になると、自分で稼いだお金を自分で管理する必要があります。
しかし、学生時代のアルバイトと比べると金額が大きくなるため、「どのくらい貯金すればいいの?」「初任給はいくら手元に残るの?」など、疑問点も出てくるのではないでしょうか?
特に、新卒で社会人になったばかりの人はお金の管理に慣れていないため、正しい知識と貯金の習慣を身につけることが大切です。
そこでこの記事では、新卒の平均貯金額や初任給の手取り額、貯金を増やす方法などを詳しく解説します。
新卒1年目の生活費の詳細や理想の貯金額、年代別の貯金額も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
新卒はどのくらい貯金すればいいの?

新社会人として自分の収入で生活するようになると、「周りの人はどのくらい貯金してるの?」「初任給のうちいくらを貯金すればよいの?」といった疑問が出てくると思います。
まずは新卒の初任給と平均貯金額について見ていきましょう。
新卒の初任給と平均貯金額
社会人一年目の平均的な貯金額は約62万円が目安です。
初任給の金額は業種や企業規模、学歴などで変わるため、1年目から100万円以上の貯金をする人もいれば、年間の貯金額が0円になってしまう人もいます。最も多いのが50〜100万円の範囲で、全体的な平均額が約62万円です。
年間で約62万円の貯金をするには、1ヶ月あたり約5万円ずつ貯金する必要があります。まずは初任給の手取り額を計算して、自分が無理なく貯金できる金額はどのくらいなのか把握しておきましょう。


初任給はどのくらい手元に残る?

社会人の給与は全額が手元に残るわけではありません。
給与の支給額から税金や社会保険料が差し引かれるため、額面の支給額よりも何割か少ない金額を受け取ることになります。
以下で新卒の初任給はどのくらいが手元に残るのか見ていきましょう。
新卒では初任給の手取りが一番多い!?
実は、新卒の初任給はその後の給与と比べて手取り額が多くなる場合があります。これは、多くの企業で社会保険料の控除が実際の給与支給の翌月分から開始されるため、初任給のみ控除されないことが多いからです。
まずは額面給与と手取り額の違いをおさえておきましょう。
手取り額:額面給与から所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれた後に実際に受け取る金額
初任給の給与からは所得税は差し引かれていますが、社会保険料の控除は通常は5月分の給与から始まるため、初任給は手取りが多くなります。最初の給与は少し多くもらえるため、貯金を始める絶好のチャンスと言えるでしょう。


新卒の生活費は結構かかる

社会人になると自分の生活費は自分の給与から支払い、残った金額を貯金していくことになります。
学生の頃と比べて生活費が増える場合が多いため、支出をしっかり管理し、計画的にお金を使うことが重要です。
以下で社会人一年目でどんな生活費が必要になるのか見ていきましょう。
社会人一年目にかかる生活費は?
一人暮らしの社会人が年間で支払う生活費の平均的な費用を表にまとめると以下のようになります。
| 支出項目 | 平均的な年間の支出額 |
| 食費 | 52万円 |
| 住居費 | 43万円 |
| 光熱費 | 12万円 |
| 家具・家電製品 | 6万円 |
| 保険料・医療費 | 8万円 |
| 交通費・通信費 | 26万円 |
| 被服費 | 8万円 |
| 娯楽費・交際費・その他 | 48万円 |
| 合計 | 203万円 |
実際の金額は個人差や地域による差もあります。表を参考に社会人一年目でどのくらいの生活費が必要になるか計算してみましょう。


新卒から貯金はできるの?

社会人一年目から効率的に貯金をしていくためには、どのくらいの金額を貯金すべきか大まかに把握しておくことが大切です。
以下で年代別の貯金額や新卒の理想の貯金額を見ていきましょう。
年代別平均貯金額の比較
厚生労働省による国民生活基礎調査の結果では、世帯主の年齢ごとの平均貯蓄額は以下のようになっています。
| 世帯主の年齢 | 世帯あたりの平均的な貯蓄額 |
| 29歳以下 | 179万円 |
| 30〜39歳 | 530万円 |
| 40〜49歳 | 650万円 |
| 50〜59歳 | 1,075万円 |
| 60〜69歳 | 1,461万円 |
| 70歳以上 | 1,233万円 |
このように、世帯主の年齢が高くなるにつれて貯蓄額は増えていく傾向があるものの、年代ごとに増加幅が異なります。
特に20代後半〜30代にかけての時期は結婚や子育てに費用がかかることが多く、貯蓄額の増加幅が緩やかになる傾向があります。
また、60代を過ぎると職場で第一線を退いたり定年退職したりすることから、貯蓄額が減少する世帯が一般的であることが分かります。
新卒の理想の貯金額は?
新卒の理想の貯金額は、1年目には目安として手取りの3割前後、約50〜70万円となるでしょう。早い段階から貯金の習慣を身につけておくことで、将来の出費や転職などに備えるための資金となります。
30代〜40代になると、結婚のために300万円程度の費用が必要になります。自家用車を購入するとさらに300万円程度の出費となります。子どもが生まれたら教育費として1,000万円〜1,800万円程度、マイホームを購入するならトータルで3,000万円〜5,000万円程度の費用が必要になるでしょう。
こういったライフイベントに対応しながら、旅行や趣味の費用なども捻出できる金額が理想的な貯金額になるでしょう。


新卒が貯金を増やすための方法5選

貯金を効率的に増やすには、いくつかコツがあります。
ここでは、新社会人でも実行しやすい貯金を増やす方法を紹介しますので、参考にしてください。
毎月の収支を確認しよう
貯金を増やすために大切なのは、毎月の収入と支出を正確に把握することです。
まず、収入から家賃や光熱費、インターネットやスマホ代などの固定費を差し引きます。次に、食費や交際費、娯楽費などの変動費を差し引くと、その月に自由に使える金額が残ります。
もし自由に使える金額が十分に残らないなら、貯金をするためには節約をしたり固定費を見直したりする必要が出てきます。まずは毎月の収支を確認して、どのくらいを貯金に回せるかチェックしてみましょう。
貯金する目標の金額を決めよう
貯金を続けるためには、明確な目標を設定することが重要です。
たとえば、「1年目は平均貯金額の60万円を目標に貯める」「3年後に海外旅行に行くために別に30万円貯める」など、具体的な金額と期限を決めましょう。
先取り貯金を利用しよう
先取り貯金とは、給料が入ったらすぐに一定額を貯金用の口座に移動させる方法です。残った金額から固定費や生活費を支払うことで、毎月確実に目標の金額を貯金できます。
可能ならば貯金専用の口座を作って、その口座からは引き出さないルールにしておくと効果的です。貯金専用口座なら残高がそのまま貯金額になりますので目標の達成状況も一目瞭然です。
銀行によっては自動的に一定額を積立できるサービスもありますので、活用してみるのもよいでしょう。
家計簿アプリを利用しよう
家計簿をつけると毎月の支出が可視化されて管理しやすくなります。無駄な支出がなかったか、予算に無理はないかなど、家計簿でじっくり確認してみましょう。
スマホで家計簿をつけられるアプリを利用すれば、気軽に始められて続けやすいのでおすすめです。さらに、レシートのデータを取り込んで自動的に記録できて便利です。支出を項目別にグラフで管理できる機能があるアプリもあります。
手書きの家計簿の方が続けやすいという人もいるかもしれません。自分に合った方法で記録を残し、支出を管理することで、貯金に回せるお金を増やしましょう。
資産運用を始めよう
資産運用とは、貯めたお金で株式や債券、投資信託などを購入して利益を得る方法です。貯金に慣れてきたら、資産運用を始めることでさらに効率的に資産を増やしていくことができます。
投資が初めての人におすすめなのは、少額から始められるNISA(少額投資非課税制度)です。NISAでは、年間の投資枠内の利益が非課税になるため、税金面でも有利に資産形成ができます。一般的な投資口座では一定額以上の利益が発生すると確定申告が必要になりますが、NISA口座を利用すれば原則として確定申告が不要なため、投資初心者にもおすすめです。
もらったボーナスは貯金しよう
多くの企業では入社一年目の新卒社員にもボーナスを支給しています。ボーナスは夏と冬にまとまった金額が支給されるため貯金を増やすチャンスです。
ボーナスの全額を貯金する必要はありませんが、計画的に活用して年間の貯金額も増やしていきましょう。


まとめ
この記事では、新卒の貯金について効率的に貯めるコツや平均的な貯金額などを詳しく解説しました。
社会人1年目の平均貯金額は約62万円です。この目標を達成するには、手取りの約3割を貯金に回すことを目安にしましょう。
手取りとは給与の支給額から税金や社会保険料を差し引いて手元に残る金額です。初任給や社会人一年目の給与は手取りが多くなるため、このチャンスを活かして早い段階で貯金の習慣を身につけておくのがおすすめです。
新社会人の生活費は予想以上にかかることが多いため、家計簿をつけて支出を把握することが大切です。効率的に貯金を増やすために、先取り貯金やスマホの家計簿アプリを利用するのもおすすめです。
貯金に慣れてきたら、NISAをはじめとした資産運用にチャレンジすることで、さらに資産を増やしていくことができるでしょう。
ぜひこの記事でまとめたことを参考にしていただき、自分に合った貯金の方法を見つけてください。