
「新卒を採用したいと思っているけれど、どんな流れで採用を進めたらいい?」
新卒を採用するにあたって、どのような流れで選考を進めていけばいいのかわからず困ってしまうことはありませんか?
新卒採用は、同じような時期に多数の企業が選考を行うため、滞りなく選考を進めていくことが大切です。
そのためには、新卒の採用の流れや準備まで、しっかりと把握しておかなくてはなりません。
そこでこの記事では、新卒採用に悩む採用担当者の方に向けて、新卒採用の流れを丁寧に解説していきます。
この記事を読み、新卒採用の流れをしっかりと把握することで、スケジュールを崩すことなくきちんと選考を行い、自社に合った人材を採用することができるようになります。
ぜひ最後までお読みください。
新卒採用の流れについて
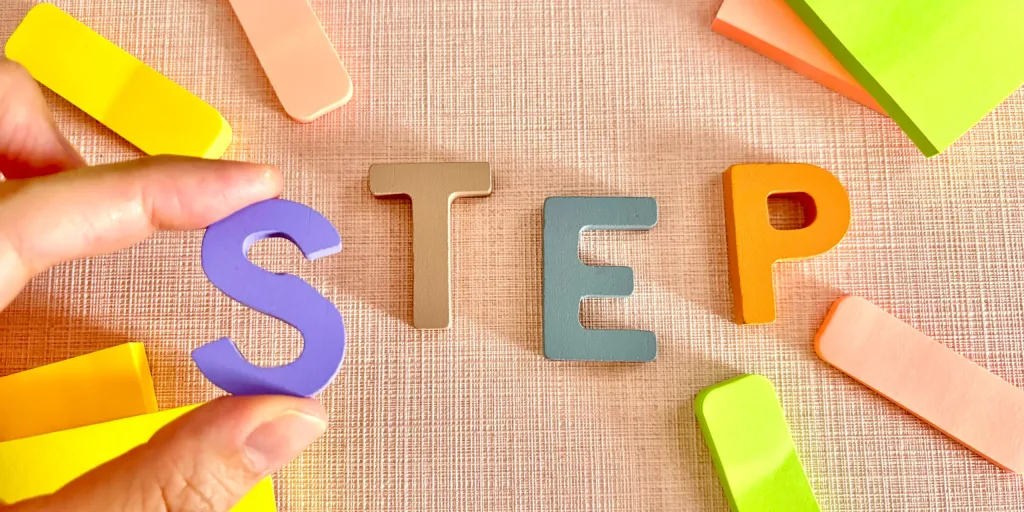
まずは新卒採用を行うにあたって、必ず把握しておきたい新卒採用の流れを紹介していきます。
新卒採用の流れは以下の通りです。
【新卒採用の流れ】
- 採用の戦略を立てる
- 採用の計画を立てる
- 募集する
- 選考する
- 内定者のフォロー
- 入社
- 入社後のフォロー
それぞれ詳しくみていきましょう。
採用の戦略を立てる
新卒を採用するにあたって、一番最初に行うのは「採用の戦略を立てる」ことです。
なぜなら、人は採用してからすぐに一人前になるのではないからです。
今年採用活動を行い、来年4月に入社した社員が3年、5年、10年で社内でどのような働きをしてもらいたいかを考えておかなければ、必要な人材が不足してしまいます。
採用戦略では、次のようなポイントを抑えておきます。
・経営戦略に合った採用人数
・どのような人材を採用すべきか
・採用にあたってかけるべき予算
・配属先

採用の計画を立てる
採用戦略が決まったら、その戦略に合わせて計画を立てます。
採用計画は、戦略よりも具体的に一つ一つのステップを決定していくものです。
例えば以下のようなものを決めておきます。
・選考方法と評価基準
・採用にかける予算
・採用スケジュール
・採用方法
・内定者のフォロー体制
・入社後のフォロー体制
・採用にあたっての実績と分析を行うタイミング
募集する
採用の計画が立てられたら、募集を始めます。
新卒採用では、まずは母集団形成を行うことが大切です。
母集団形成とは、自社に興味がある人材を集めることで、新卒採用では以下のような方法で母集団形成を行います。
・新卒採用専用のホームページやSNSを立ち上げる
・合同企業説明会に出展する
・就職ナビサイトに出稿する
・企業説明会を開催する
・大学に求人票を出す
・学内説明会を開催する
上記の方法の中から、予算などに応じた方法を複数選び、募集を行いましょう。
選考する
募集で応募者を集めることができたら、選考を行い採用者を決定します。
採用担当者によって評価のポイントが変わってしまうことがありますから、あらかじめ評価のポイントを決めて共有しておきましょう。
選考方法は次のようなものがあります。
・適性検査
・グループ面接
・最終面接
上記のような選考を行い、内定者を決定しましょう。
内定者のフォロー
内定者が決定したら、内定通知を出して入社する人材を確保します。
中途採用とは違い、新卒の場合は内定が出てから実際に入社するまで、期間が空いてしまいますから、内定者へのフォローが大切です。
一般的には10月に内定を出すことが多いのですが、その場合実際の入社まで5ヶ月ほど空いてしまいます。
入社
4月になれば、いよいよ新卒が入社します。
新卒の場合は4月1日に入社式を行うことが一般的です。
入社式を行うことで、新卒ならではの「同期」としての一体感が生まれますし、気持ちを新たに仕事をがんばるモチベーションにもなりますから、入社式はなるべく行うことをおすすめします。
入社後のフォロー
特に若年層の退職が多いとされる入社3年目までは定期的なフォローを行うことがおすすめです。
【大手・中小・外資別】新卒採用スケジュール

Planning Chart for Financial Project
新卒採用の流れを理解した上で、次は新卒採用のスケジュールをみていきましょう。
実は新卒採用スケジュールは、大手企業、中小企業、外資系企業で少しずつ異なります。
それぞれの採用スケジュールと、その特徴について2027年卒業の方の例を用いて解説します。
大企業における新卒採用の一般的な流れ
【大企業における新卒採用スケジュール】
| 時期 | 内容 |
| 2025年6月~2026年2月 | インターンシップ開催 |
| 2026年3月~2026年5月 | 会社説明会・広報 |
| 2026年6月~2026年9月 | 選考(適性試験・書類選考・面接) |
| 2026年10月〜 | 内定通知 |
大企業の場合、政府が主導する新卒採用のスケジュールに沿って動きます。
実際の選考は6月~9月ですが、インターンシップなどは前年度から行い、積極的に学生にアピールしているのが特徴です。
中小企業における新卒採用の一般的な流れ
【中小企業における新卒採用スケジュール】
| 時期 | 内容 |
| 2025年6月~2026年2月 | インターンシップ開催 |
| 2025年12月~2026年2月 | 春採用の会社説明会・広報 |
| 2026年2月~4月 | 春採用の選考(適性試験・書類選考・面接) |
| 2026年4月頃〜 | 春採用の内定(内々定)通知 |
| 2026年6月~8月 | 秋採用の会社説明会・広報 |
| 2026年8月~10月 | 秋採用の選考(適性試験・書類選考・面接) |
| 2026年10月頃〜 | 秋採用の内定通知 |
中小企業は、大企業と時期をずらして、春と秋の2回採用選考を行うことが多くあります。
これは大企業の選考時期は学生がそちらに取られてしまうため、応募者を確保するために行うものです。
秋採用は、大企業の内定が貰えなかった学生を再度集めることを目的に行います。
外資系企業における新卒採用の一般的な流れ
【外資系企業における新卒採用スケジュール】
| 時期 | 内容 |
| 2025年6月~12月 | インターンシップ開催 |
| 2025年8月~2026年5月 | 会社説明会・広報 |
| 2025年10月~2026年5月 | 選考(適性試験・書類選考・面接) |
| 2026年2月~5月 | 内定通知 |
外資系企業の多くは、政府主導の就活ルールを守らず、早期から採用活動を行うところが多数あります。
採用スケジュールを前倒しにすることで、優秀な学生を早期に確保することが目的です。
政府主導のルールは強制力があるものではないため、今後も流れは変わらないでしょう。

新卒採用での準備や決めること
新卒採用を行う上で、どのような準備を行い、何を決定しておけばいいのでしょうか?
新卒採用で必要となる準備や決めることは次の通りです。
・募集要項の決定
・選考フローの明確化
・評価基準の決定
・母集団形成の選出
・内定者フォローの実施
それぞれ詳しくみていきましょう。
採用スケジュールの決定
新卒採用を行う時は、まず初めに採用スケジュールを決定しましょう。
採用スケジュールは企業規模によって時期がずれますので、「【大手・中小・外資別】新卒採用スケジュール」を参考におおまかな時期を決めたら、具体的な日時を決定していきましょう。
そのような学生にも選考に参加してもらうため、通年採用を行う企業もありますから、自社が考える採用戦略に基づいてスケジューリングを行うとよいでしょう。
募集要項の決定
次に行うのは募集要項の決定です。
自社の採用戦略に応じて、求める新卒はどのような人かを決定していきます。
例えばつぎのような条件で考えていきましょう。
・学部学科系統(全学科応募可能、指定学部など)
・募集する職種(総合職、専門職)
・必要なスキル(普通自動車免許、語学力、資格など)
・居住地(配属地)
・求める人物像
・学業成績
選考フローの明確化
選考フローの明確化も行わなくてはなりません。
新卒採用は、中途採用とは違い、応募者が多数であるという特徴があります。
また、将来性やポテンシャルといった評価が難しいものを採用基準にしなくてはならないため、求める人材と実際に内定を出した人とのミスマッチが起こりやすくなるのです。
評価基準の決定
新卒採用は、将来性やポテンシャルといった数値化しにくいものを採用基準にしなくてはなりません。
そのため、評価基準をしっかりと設けた上で、採用担当者全員が共有することが大切です。
まずは自社の採用戦略に応じた求める人物像を決定した上で、それに合わせた評価基準を決めておきましょう。
母集団形成の選出
優秀な新卒を獲得するためにも、自社に興味を持つ母集団形成を行うことがとても大切です。
そのためにも、母集団形成を行うための方法を決定しておきましょう。
・新卒採用専用のホームページやSNSを立ち上げる
・合同企業説明会に出展する
・就職ナビサイトに出稿する
・企業説明会を開催する
・大学に求人票を出す
・学内説明会を開催する
内定者フォローの実施
せっかく新卒採用を行ったのに、内定辞退が多数出てしまうといった事態を防ぐためにも、採用前から内定者フォローを行う体制を整えておきましょう。
新卒採用のスケジュールの事前準備について

ここからは新卒採用のための具体的なスケジュールと、そのために何を事前準備していくべきかを紹介していきます。
新卒採用は中途採用とは違い、ある程度時期が決まっているものですから、事前準備をしっかり行うことでスムーズに選考を進めていくことが大切です。
まずはスケジュールと必要な準備をしっかり行っておきましょう。
新卒採用の具体的なスケジュール
前年3〜8月:前年の振り返りとインターンシップ
まずは前年度の新卒採用がどうだったのか、採用人数や採用フローなどを振り返り、分析を行います。
分析を行うことで、自社の新卒採用をブラッシュアップさせることができますから、必ず振り返りを行いましょう。
同時にインターンシップも行います。
インターンシップは「採用選考を視野に入れた評価材料を得ること」が可能となり、新卒採用の中でかなり重要なものとなってきました。
インターンシップは大企業ほど早めのスケジュールで学生の確保に乗り出します。
出遅れることのないよう、早めに準備を行いましょう。
前年9〜11月:広報の準備
前年度の9月からは広報の準備を行います。
ただ社名を知ってもらうだけでなく、求める人物像や企業理念などをきちんと伝えることで、自社に合う学生が集まるようにするのが大切です。
広報活動は次のような準備が必要です。
・企業紹介パンフレットの作成
・企業紹介リーフレットの作成
・合同説明会への出展準備
・採用サイトを作成
・採用動画を作成
前年12月〜2月:最終調整
前年度の12月から今年度の2月にかけては最終調整を行います。
広報のために準備した印刷物などをチェックしたり、面接会場の確保、面接を担当する社員のスケジュール調整などを行いましょう。
各部署ごとに必要な人員数や、採用したい人物イメージなども確認し、まとめておきます。
当年3月〜5月:採用活動開始
3月からはいよいよ採用活動がスタートします。
エントリー数を増やすために、企業側も積極的に広報活動を行いましょう。
学生の応募数が少ない場合は、会社説明会などの広報活動の結果を確認する、採用サイトのアクセス解析を行うなどして、広報活動の効果を分析し、適宜改善を行いましょう。
当年6月〜9月:内定者フォロー
6月からは採用選考が進み、内定者を決定していきます。
内定通知を出したら、内定者のフォローを行いましょう。
新卒採用のスケジュールを組むポイント

大手企業を志望する学生は6月のインターンに参加
2025年卒の新卒採用からインターンシップの定義が変わり、インターンシップに参加した学生の情報を採用選考に利用することが可能になりました。
そのため新卒採用でのインターンシップの重要性が高まっており、特に大手企業を志望する学生は6月のインターンに参加することが大切になっています。
体育会系部活の学生には引退後にアプローチする
体育会系部活の学生は協調性や責任感が高く、積極的に採用したいと考えている企業も多いでしょう。
部活動に力を入れている体育会系の学生は、強豪校になればなるほど部活動の引退時期は遅くなります。
体育会系部活の学生を採用したいなら、引退後にアプローチを行うようにしましょう。
主なインカレの大会が行われるのは、次の時期です。
【主なインカレの大会時期】
| 大会 | 開催時期 |
| 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 毎年秋頃 |
| 全日本大学野球選手権大会 | 毎年6月頃 |
| 全国国公立大学選手権水泳競技大会 | 毎年8月頃 |
| 全日本学生テニス選手権大会 | 毎年8月頃 |
公務員落ちの学生には福利厚生の良さを伝える
公務員を目指して試験を受けたけれど、落ちてしまった学生を採用したい場合は、福利厚生の良さを伝えることが有効です。
公務員を目指す学生は「安定」「休日がしっかりとれる」「福利厚生が充実している」ことを求めていることが多いという特徴があります。
自社でも福利厚生が充実していることを伝えることで、公務員に落ちた学生の応募を増やすことができるのです。
【一般的な公務員試験のスケジュール】
| 3月 | 出願 |
| 5~6月 | 一次試験 |
| 7月以降 | 二次試験 |
| 8~9月 | 内定 |
他社の動向についてチェックする
採用活動を行う上で、他社の動向についてチェックすることも大切です。
同業で同規模のライバル企業の動向はもちろん、大企業の動向も確認しておくことをおすすめします。
他社の動向をチェックすることで、日程が被ってしまうことを防ぐことができますし、よい採用活動を行っていれば自社に取り入れることもできます。
大手企業の動向をチェックすることで、採用されなかった学生獲得を狙ったスケジュール調整も可能です。
前年度の新卒採用の取り組みを振り返る
今年度の新卒採用を始める前に、必ず前年度の取り組みを振り返るようにしましょう。
採用スケジュールは年々変化しており、採用活動は早期化しているのが現状です。
また、インターンシップを選考の材料とすることが認められたため、インターンシップの重要性も高くなっています。
具体的には次のようなことを確認しておきましょう。
・効果的な広報活動はどれか
・採用につながった取り組み
・学生からの反応はどうだったか
・スケジュールは適切だったか
上記のようなポイントを確認し、今年度の新卒採用に活かしていきましょう。

新卒採用活動で注意すること

新卒の採用活動では、中途採用とは違い注意しなくてはならない点があります。
新卒の採用活動で注意すべき点は次の通りです。
・新卒採用の業務を効率化させる
・新卒採用の市場の変化に対応する
それぞれ詳しくみていきましょう。
新卒採用の成果が出ない場合は採用のやり方を考え直す
新卒採用の成果が出ない、エントリーする学生の集まりが悪いといった場合は、採用のやり方を考え直す必要があります。
採用活動でまず大切なのは、自社に興味を持つ母集団形成を行うことです。
母集団形成がうまくいかなければ、エントリーする学生が少なく、選びようがなくなってしまいます。
新卒採用の成果が出ないという場合は、採用のやり方自体をまずは考え直して、新しい施策を行いましょう。
新卒採用の業務を効率化させる
新卒採用は業務が多岐にわたりますし、複数の業務が同時進行しなくてはならない場合もあり、採用担当者への負担が大きくなります。
業務を効率化することは、スムーズに新卒採用を進める上でとても重要です。
新卒採用の市場の変化に対応する
新卒採用の市場は毎年変化していきます。
その変化に対応することが、新卒採用を成功させるためには必須です。
採用市場は景気や新しいサービスの対応で大きく変化します。
例えば新型コロナウイルスの流行により、新卒採用ではオンライン活用が急速に増えました。
オンラインを活用することで、遠方の学生とも気軽に接点を持ち、よりよい応募者を集めることができるきっかけにもなっています。
【新卒の本音を聞き出そう】面接で使える効果的な質問集

・自己理解ができているか把握する
まずは自己理解ができているか把握するための質問を紹介します。
自己理解とは、自分の長所や短所、強みといった部分をどれほど深く理解できているかを確認することです。
自己理解を深めることで、自分がどこを伸ばすべきか、どこをカバーしていくべきかを把握することができ、自己研鑽を高めることができます。
自己理解をどれくらいしているかを確認することは、新卒採用ではとても重要といえます。
質問例
「これまでの経験で最も成長を感じた出来事とその理由を教えてください」
・仕事に関する価値観や意識を聞き出す
次に紹介するのは、仕事に関する価値観や意識を聞き出すための質問です。
自社に合う人材をピックアップするためには、価値観を聞き出してマッチする人を選ぶことがとても効果的です。
仕事に対してどのような価値観や意識を持っているのか、自社に合った価値観なのかをしっかりと確認していきましょう。
質問例
「仕事を通じて社会にどのような貢献をしたいですか」
・思考パターンやストレス耐性をチェックする
仕事をしていくうえで、ストレスを避けることはできません。
ストレスがかかった時にどのように思考して対処するか、ストレスにどれくらい耐性があるかをチェックすることも大切です。
ストレス耐性が高い人であれば、ある程度の仕事のストレスは受け流しつつ、改善方法を考えることができます。
また、困難に対してどれくらい立ち向かう力があるかも確認することが可能です。
質問例
「意見が対立した時、どのように解決に導きますか」
・主体性や計画性を把握する
仕事をするうえで、どれくらい主体性を持って取り組めるか、計画的に取り組めるかという点も新卒採用では確認しておきたい点です。
質問例
「新しい環境で何かを始める時、どのような準備をしますか」
・成長意欲の有無や高さを測る
成長意欲の有無や、意欲の高さを測ることも大切です。
なぜなら新卒採用では将来性やポテンシャルに期待できる人を採用するしかないため、成長意欲の有無やその高さは今後のキャリア形成に大きな影響を与えるからです。
成長意欲が高いほど、入社後の成長に期待ができます。
成長意欲の有無や、高さについても質問しておきましょう。
質問例
「失敗から学んだ経験で印象に残っているものを教えてください」

早期選考を実施するメリット
早期採用を検討している採用担当者も多いかと思います。
早期採用を実施するにはいくつかのメリットがあり、自社の希望に合うのであれば、早期選考を実施することもおすすめです。
早期選考を実施するメリットは次のようなものが挙げられます。
・早期に必要な人材を確保できる
・PDCAを回して採用活動の質を高めることができる
早期採用を行うことで、他者よりも早く人材確保に乗り出し、優秀な学生を確保しやすくなるのが最大のメリットです。
また早期に人材を確保しておくことで、後々の研修等に余裕を持つことも出来ます。
採用活動を見直し、改善を繰り返すことで、採用活動の質を高めることも可能です。
まとめ
新卒採用の流れについて、準備から詳しく解説しました。
新卒採用は業務が多岐にわたり、時期も決まっているためとても大変です。
しかし新卒採用を計画的に行うことは、企業の経営戦略上とても重要なことなのです。
この記事を参考にしっかりと新卒を採用し、優秀な人材を確保して企業として成長をしていきましょう。


