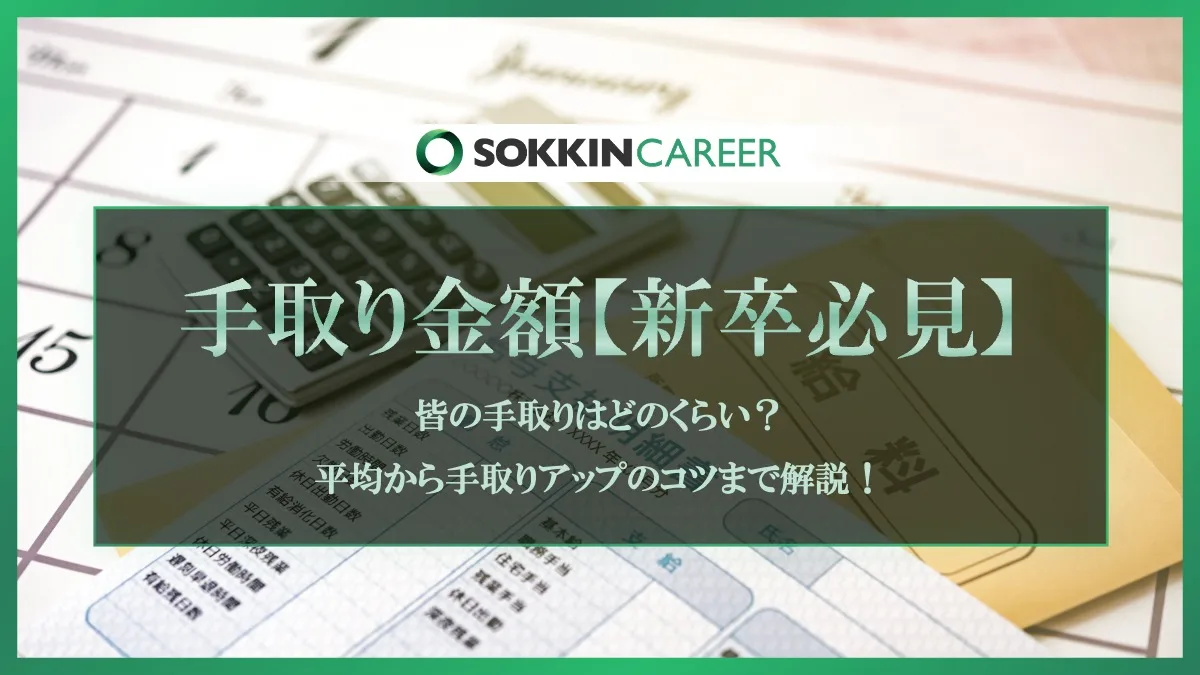いざ社会人として歩み始めるとき、誰もが気になるのが「手取り額」です。
実際に給与を受け取った新卒の方の多くが、「思ったより少ない…」と感じているかもしれません。こうした背景には、給与に関する仕組みがあります。
正確な手取りを把握するには、この仕組みを理解しておくことが大切です。
この記事では、手取り・総支給額・給与所得の基本と違いから、「新卒のシーン別給与平均」「手取りアップのちょっとしたコツ」まで、わかりやすく解説していきます。

そもそも「手取り」とは何?総支給額や給与所得との違いについて

給料について誰かと話すとき、「手取りいくら?」という言葉を耳にしたことはありませんか。
この「手取り」の正しい意味を把握している新卒の方はまだまだ少ない印象です。特に多いのが、「総支給額」や「給与所得」など、似たような用語と混同しているケースです。
ここでは、手取り・総支給額・給与所得の意味と違いについて、できるだけわかりやすく解説します。また、覚えておきたい用語として、「給与所得控除」についても紹介するので、新卒の方はぜひ参考にしてください。
「総支給額」とは
「総支給額」とは、会社から支払われる基本給に、各種手当を加えた合計金額を指します。
基本給に、各種手当(残業手当や通勤手当、住宅手当など)をすべて足したものが総支給額です。各種手当の金額は、全員共通のものから、人によって支給されるものもあるため、常に変動します。
入社シーズンになると、各メディアで新卒の給与が話題になりますが、そのほとんどが総支給額です。総支給額の正しい意味を理解しておけば、給与明細やこうしたニュースを正しく読み解けるようになります。
「給与所得」とは
「給与所得」とは、会社から支払われた給与から、一定の経費を差し引いた金額です。
正社員として働く人が受け取る「基本給・各種手当・ボーナス(賞与)など」は、すべて「給与」として扱われます。この給与から、実際の経費の代わりとなる「給与所得控除」(後ほど詳しく解説)を差し引いた金額が、「給与所得」になります。
この給与所得が年末調整や確定申告の際に、各種税金を決める基準となるのです。
「手取り」とは
手取りとは、会社から支払われる総支給額から、税金と社会保険料を差し引いた金額です。
手取りは、社会人が自由に使えるお金で、ここから家賃や食費、貯金などを捻出します。そして、多くの方は総支給額と手取りのギャップに驚きを覚えるかもしれません
社会人として生活していくうえで、手取りは大切です。今後、転職を考える際は、総支給額ではなく、手取りでいくらもらえるかを意識して選ぶようにしましょう。
「総支給額」「給与所得」と「手取り」の違い
給与に関する用語には、「総支給額」「給与所得」「手取り」がありますが、それぞれ意味が異なります。各用語を混同しないように、基本をしっかりと押さえておきましょう。
| 用語 | 意味 | ポイント |
| 総支給額 | 税引き前の給与の総額 | 支給される給与のベース |
| 給与所得 | 税金を計算するための所得額 | 所得税・住民税のベース |
| 手取り | 実際に受け取る金額 | 日々の生活費のベース |
新卒の方は、まず「手取り」に注目してください。基本的に手取りは、総支給額の「約7〜8割程度」だといわれています。ただし、新卒など状況によっては個人差があります。
また「自分がいくら稼いでいるのか」を知りたい場合は、「総支給額」を確認しましょう。税金などが引かれる前なので、あなたの本来の収入がわかります。
最後に「給与所得」は、税金を計算するための金額です。会社員の場合、通常は年末調整で税金の手続きが完了するため、あまり意識することはありません。しかし、意味を知っておけば、税金や年末調整の仕組みも理解しやすくなります。
所得で引かれている「給与所得控除」ってなんのこと?
「給与所得控除」とは、働くうえで必要な経費を、あらかじめ引いてくれる制度です。
仕事の各種経費(例:通勤・スーツ・書籍など)は、個別に証明することが難しいため、国が一律で「みなし経費」として、一定額を差し引く仕組みとなっています。
この制度は、会社から給与をもらっている人全員に適用されます。また、年末調整で自動的に処理されるため、特別な手続きは不要です。
この給与所得控除を差し引いたあとの金額が給与所得となり、それをもとに所得税や住民税を計算します。
詳細な給与所得控除に関しては、下記のURLからご覧ください。


実際に総支給額から手取りまでで何が引かれる?

「総支給額がすべて自分の口座に入ってくれればいいのに」、そう考えたことのある社会人は少なくありません。
実際には、さまざまな税金や社会保険料が引かれたうえで、手取りとして受け取ることになります。ここでは、そんな総支給額から何が引かれるのか、代表的な7つの項目を解説します。
①健康保険料
健康保険は、病気やケガのときに医療費の一部をカバーしてくれる制度です。
会社員の場合は、主に以下のどちらかの制度に加入します。
- 協会けんぽ:主に中小企業が加入
- 健康保険組合:主に大企業が加入
加入先によって、保険料率や計算方法が異なるため、注意してください。
今回は、協会けんぽ(令和7年度・39歳以下)のケースを見ていきましょう。
新卒社員Aさんは、東京都の中小企業に勤めていて、毎月の給与が18万円です。
ここから、毎月の健康保険料を「標準報酬月額×健康保険料率」で算出します。
Aさんの場合、標準報酬月額は「180,000円」の等級に該当し、健康保険料率は「9.91%」です。(標準報酬月額は「毎年の4月〜6月の平均賃金」をもとに決定します)
- 18万円(標準報酬月額)× 9.91%(健康保険料率)=「1万7,838円(全体)」
- 1万7,838円(全体)÷2(労使折半)=「8,919円(本人負担)」
健康保険料は、会社と本人が半分ずつ負担する仕組みのため、Aさんが実際に支払う健康保険料は「8,919円」となります。
②厚生年金保険
厚生年金保険は、将来的な年金の支給に備えるための制度です。
会社員の場合は、原則として厚生年金に加入します。
厚生年金保険料は、「標準報酬月額×厚生年金保険料率」で算出します。
先ほどの新卒社員Aさん(東京都の中小企業で勤務・給与18万円)の場合、標準報酬月額は「180,000円」の等級に該当し、厚生年金保険料率は「18.3%」(固定)です。
- 18万円(標準報酬月額)×18.3%(厚生年金保険料)=「32,940円(全体)」
- 32,940円(全体)÷2 (労使折半)=「1万6,470円(本人負担)」
厚生年金保険料も、健康保険と同様に労使折半します。よって、Aさんが実際に負担する金額は「1万6,470円」です。
③労災保険
労災保険は、仕事中・通勤中のケガや病気、事故などに対して、補償を受けられる制度です。
パートやアルバイトも対象のため、すでに聞いたことがある人は多いでしょう。
例えば、業務中に転んで骨折したり、通勤途中に交通事故に遭ったりした場合に、治療費や休業補償が支払われます。
詳細な労災保険料率に関しては、下記のURLからご覧ください。
参考:労災保険率表|厚生労働省
④雇用保険
雇用保険は、失業や育児、介護など、生活を支えるための制度です。
主に、求職者給付・教育訓練給付・育児休業給付・介護休業給付などがあります。
雇用保険保険料は、会社と本人が半分ずつ支払う仕組みです。ただし、他の社会保険と違って負担が少なく、保険料率も低い傾向にあります。
詳細な雇用保険料率に関しては、下記のURLからご覧ください。
参考:令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内|厚生労働省
⑤介護保険
介護保険は、介護が必要になったときのための制度です。
40歳になると、自動的に介護保険への加入が義務づけられ、給与から保険料が天引きされます。(新卒の方は40歳未満なのでかかりません)
保険料は収入に応じて計算され、健康保険料と同時に引かれるケースが多いです。
将来、介護が必要になったときには、この制度によって訪問介護や施設費用の一部が助成されます。新卒の段階では意識しづらいですが、高齢化社会では必要な備えともいえる保険です。
⑥所得税
所得税は、個人の収入に対して発生する税金です。
収入に応じて、税率が上がる「累進課税制度」が採用されています。
会社員の場合、毎月の給与から所得税が天引きされ、これを「源泉徴収」と呼びます。
所得税の計算は、給与所得から「各種控除(基礎控除や扶養控除など)」を引いた「課税所得」に、「税率(例:195万以下なら5%)」をかけて算出する仕組みです。
詳細な税率に関しては、下記のURLからご覧ください。
⑦住民税
住民税は、都道府県や市区町村に納める地方税です。
前年の所得に基づいて金額が決まるため、新卒1年目などは引かれないこともあります。
会社員の場合、毎年6月に前年分の所得で住民税が確定し、その総額を12か月で割ったものが毎月の給与から天引き(特別徴収)されます。
例えば、渋谷区在住の場合、区の公式サイトから住民税を確認できます。渋谷区では、住民税の計算例も掲載しているので、ぜひ金額の参考にしてみてください。(東京在住でもあるため、同時に都民税も支払います)
また、自分の住んでいる場所の住民税が知りたい方は、「〇〇 住民税」と検索してみましょう。


実際に新卒の総支給額平均ってどれくらい?

毎月の給与として受け取る総支給額は、主に学歴や業界、地域によって大きく変わります。
厚生労働省の新規学卒者の学歴別にみた賃金によると、新卒大学生の男女平均は「24万8,300円」となっています。
しかし、これはあくまで「基本給+各種手当」を合計した金額です。この総支給額から、税金や社会保険料が引かれて実際に手取りとして口座に振り込まれます。
ここからは、学歴や業界、地域別の総支給額平均を見ていきます。
学歴別で比較
| 男 | 女 | 男女平均 | |
| 高校 | 20万5,000円 | 19万1,700円 | 19万7,500円 |
| 専門学校 | 21万9,300円 | 22万4,800円 | 22万2,800円 |
| 高専・短大 | 23万1,000円 | 22万1,100円 | 22万3,900円 |
| 大学 | 25万1,300円 | 24万4,900円 | 24万8,300円 |
| 大学院 | 29万200円 | 27万8,100円 | 28万7,400円 |
学歴によって、新卒の総支給額には一定の差があります。厚生労働省のデータを見ても、一般的には最終学歴が高いほど、初任給も高くなる傾向にあります。(令和6年調べ)
例えば、高卒での就職では18〜20万円程度のスタートが多く、専門卒や短大卒の場合は22万円前後が相場です。大学卒になると25万円前後が平均的な金額になります。大学院を修了した場合は、それよりも2〜3万円高くなることもあります。
業界別で比較
| ・建設業 | 22万7,500円 |
| ・教育、学習支援業 | 22万1,400円 |
| ・製造業 ・情報通信業 ・金融業、保険業 ・不動産業、物品賃貸業 |
22万円 |
新卒(大学)の総支給額は、業界によっても大きく異なります。初任給が高い傾向にあるのは、建設、教育、IT、金融、不動産などの業界です。これらの業界の初任給は22万円前後となっています。(令和6年調べ)
都道府県別で比較
| 東京都 | 22万500円 |
| 千葉県 | 21万1,700円 |
| 神奈川県 | 21万800円 |
参考:令和元年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況|厚生労働省
都道府県別では、東京、千葉、神奈川と、関東を中心に初任給が高い傾向にありました。(令和元年調べ)都市部では生活に関するコストがかかるため、給与水準も比較的高く設定されています。
例えば、東京都、神奈川県、大阪府などの都市部では、初任給が平均して21万円前後となるケースが多く見られます。一方で、地方では数万円程度低いのが一般的です。

コラム:新卒から1年間でどのくらい貯金ってできるの?

新卒で働き始めたばかりの人にとって、「1年間でどのくらい貯金できるのか?」は気になるテーマです。
実際のところは、手取りや生活スタイルによって大きく差が出ます。
例えば、東京で一人暮らしをしている人の手取りが16万円前後だとすると、家賃や生活費、交際費などでほとんどが消えてしまうかもしれません。
一方、実家暮らしなら各費用が大幅に抑えられるため、月5万円以上の貯金も夢ではありません。
どちらにせよ大切なのは、新卒の頃から貯金の習慣を身につけることです。
特に、毎月決まった額を先に貯金しておく「先取り貯金」はおすすめです。前述した通り、まずは収入の1割程度の貯金を、1年間継続するところから始めてみましょう。
新卒が手取りを増やすためには何をするのがいい?

新卒の手取りに物足りなさを感じる方は少なくありません。
しかし今後、ちょっとした工夫を実践し続ければ、段階的に手取りを増やすことも可能です。
手取りを増やす方法には、収入を上げることだけではなく、税金や保険料を減らす方法もあります。
ここでは、新卒が実践できる「手取りを増やすための方法」を5つご紹介します。
資格を取得しよう
資格取得は、手取りアップへの近道です。
企業によっては、特定の資格取得(ITや語学、会計など)を条件に、一定の手当が支給される「資格手当」を用意しています。今後、資格取得を考えているなら、「資格手当」に該当する資格への挑戦をおすすめします。
また、金融系などでは、資格取得が昇給の条件になっているケースも少なくありません。この場合も、まずは昇給を目指しての資格取得がおすすめです。
成果を上げて昇進を狙おう
手取りを増やすには、基本給を上げるのがもっとも確実な方法です。
そのためには、日々の仕事で成果を出し続ける必要があります。
新卒でも、積極的に行動したり提案したりすることで、少しずつ上司の評価を高めていきましょう。特に、明確な評価制度を採用している企業なら、頑張った分だけ昇給・昇進につながるかもしれません。
昇進すれば、役職手当がつくケースもあり、手取りが一気に上がる可能性もあります。
所得控除を活用しよう
- 雑損控除
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 寡婦・寡夫控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
手取りを増やすだけではなく、税金を減らす「所得控除」を活用する方法もあります。
所得控除とは、収入から一定額を差し引くことで、課税される所得を減らす制度です。
これにより、所得税や住民税が減り、相対的に手取りが増えることになります。
代表的な所得控除は、「生命保険料控除」や「医療費控除」、「ふるさと納税(寄附金控除)」などです。新卒の場合でも条件を満たしていれば、所得控除の対象となる可能性があります。
転職も視野に入れてみよう
将来的な手取りアップを考えているなら、転職もひとつの選択肢です。
新卒で考えるのは早いと感じるかもしれませんが、自分自身のスキルや経験を棚卸しする意味でも、無駄なプロセスではありません。今後、身につけたスキルや経験が、他の会社でより評価される可能性は十分にあります。
例えば、同じような仕事内容でも、会社によって基本給の金額は異なります。また、一見基本給が低くても、福利厚生や各種手当の充実度によっては、実質的な手取りが多くなるかもしれません。
副業をしてみよう
副業なら、手取り以外の収入源を確保できます。
近年では、国が副業を促進したり、会社が副業を認めたりするケースも増えています。新卒でも、副業のジャンルによっては、通常業務と並行できるかもしれません。
新卒が片手間にできる副業の収入は微々たるものですが、いずれ本業になる可能性もあるため、継続して行うことが大切です。
また、副業を始める際は、本業に支障が出ないように注意しましょう。特に、新卒の頃は、まず本業に集中し、余裕が出てきたら副業をするといった考えで問題ありません。


コラム:手取りだけじゃない!給料以外の手当てにも目を向けてみよう

新卒の頃は、手取りだけに目が行きがちですが、各種手当にも注目しましょう。
企業には、住宅手当や家族手当、資格手当など、さまざまな手当があります。
例えば、住宅手当がある場合は、家賃の一部が補助されるため、実質的な生活費が減ります。家計を圧迫するのは、主に維持費が中心なので、住宅手当は心強い味方です。手取りは同じでも、こうした手当により自由に使えるお金が増えます。
また、福利厚生も見逃せません。社食や書籍の購入補助、健康診断の充実など、間接的な支援を実現してくれます。
まとめ
手取り・総支給額・給与所得の違いや、手取り額から引かれる税金や社会保険、さらにはは、新卒の総支給額平均まで解説してきました。記事の最後には、新卒が手取りを増やす方法も紹介しています。
新卒の手取りは、総支給額に比べて少なく感じることが多いです。
しかし、総支給額から引かれる金額は、あくまで私たちの将来のために使われる大切なお金として機能します。
こうした知識を持っておけば、今後の社会人生活はもちろん、家計管理や貯蓄計画、将来的な夢の実現まで、幅広い事柄に役立ちます。
特に、手取り以外にも、各種手当や福利厚生に注目することは今後のためにも大切です。
新卒の頃から、広い視野を持って自身のキャリアについて考えてみてください。