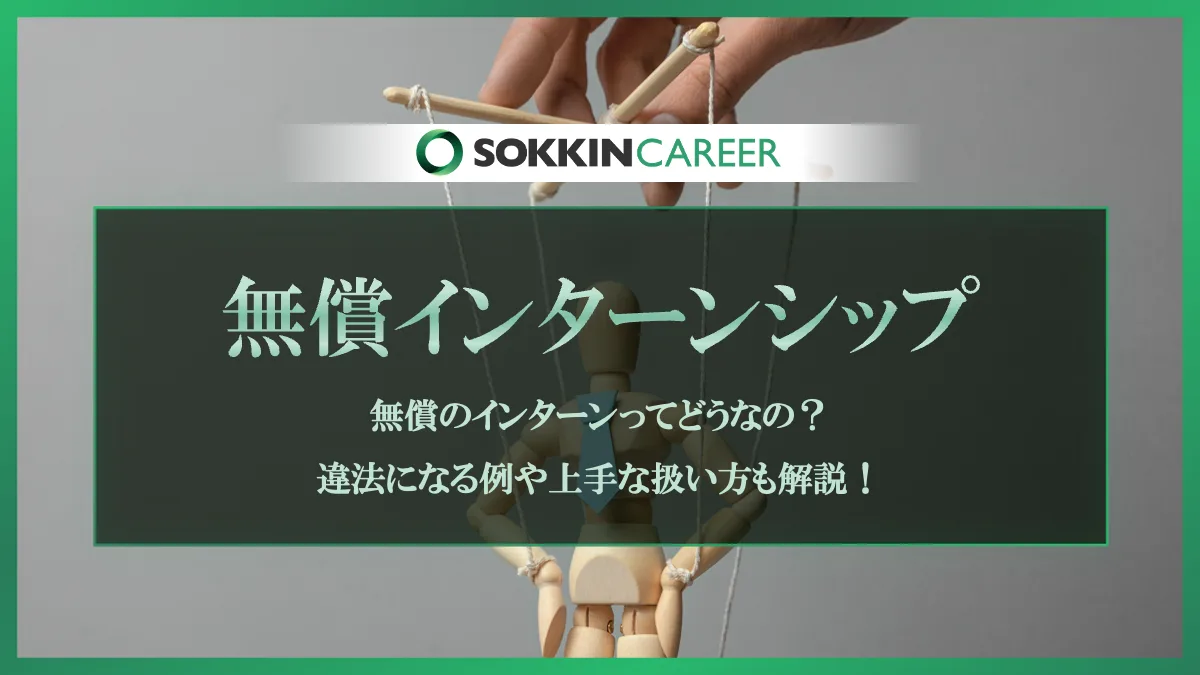就職活動においてインターンシップは重要な経験の一つですが、無償インターンについて「違法ではないの?」「参加する意味はあるの?」といった疑問を持つ学生も多いのではないでしょうか。
実際に、無償インターンには法的な問題が生じるケースもあれば、就活に大きなメリットをもたらすケースもあります。本記事では、無償インターンの実態から違法となる具体例、そして効果的な活用方法まで詳しく解説します。正しい知識を身につけて、安心してインターンシップに参加しましょう。
無償インターンと有償インターンとは

就職活動を進める中で、インターンシップへの参加を検討している学生の皆さんも多いでしょう。インターンシップには大きく分けて「無償インターン」と「有償インターン」の2つの形態があります。この2つの違いを理解することは、自分の目的に合ったインターンシップを選択するために非常に重要です。それぞれの特徴や見極め方について詳しく解説していきます。
無償インターンの特徴
無償インターンは、給与を受け取らずに参加するインターンシップです。最も大きな特徴は、業務を広く浅く体験できることです。短期間で実施されることがほとんどで、1日から1週間程度の期間設定が一般的となっています。
無償インターンでは、企業の各部署を見学したり複数の職種の業務を体験したりできます。営業部門での商談見学から始まり、マーケティング部門でのデータ分析体験、人事部門での採用業務の一部まで幅広く経験可能です。
また、グループワークやプレゼンテーション形式で進められることが多く、他の参加者との交流も深められます。企業説明会では得られない実際の職場の雰囲気や企業文化を肌で感じることができるでしょう。
有償インターンの特徴
有償インターンは、給与を受け取りながら参加するインターンシップです。特徴として、業務を狭く深く体験できることが挙げられます。実際の社員と同等の責任を持って業務に取り組むため、より実践的なスキルを身につけられます。
有給インターンシップの給与体系は、大きく時給・日給・成果報酬の3パターンに分けられます。平均的な時給は1,000〜2,000円、日給の場合は6,000〜10,000円が相場です。
成果報酬の場合は、1作業につき1,000円のものから50,000円のものまでさまざまです。ただし、インターンで求められるスキルや資格などによって報酬は変動するため、一概には言えません。

無償インターンと有償インターンの見極め方
インターンシップに応募する際、その内容が無償なのか有償なのかを事前に正確に把握することは重要です。期待していた条件と異なる場合、後々トラブルの原因となる可能性があります。確実に見分けるための方法を解説します。
求人サイトをよく確認する
インターンシップの募集要項を確認する際は、給与体系の箇所を特に注意深く読みましょう。「給与」「報酬」「手当」などの項目があるかどうかを確認してください。
求人サイトによっては、検索条件で「有給」「無給」を選択できる機能もあります。こうした機能を活用して効率的に情報収集を行いましょう。
雇用契約書をよく読む
実際に採用となった時は、雇用契約書や労働条件通知書を必ず確認してください。口約束だけでなく、書面で労働条件が明記されているかをチェックしましょう。
契約書には、勤務時間・勤務日数・給与の有無・支払い方法などが詳細に記載されています。不明な点があれば遠慮なく質問し、納得した上で契約を結ぶことが重要です。
無償のインターンの事例を紹介

無償のインターンシップの中には問題のあるケースも存在しています。採用を前提としたインターンシップであったにも関わらず、最終的に採用予定そのものがなくなってしまう事例があります。
このように教育的な目的から大きく逸脱し、実質的な労働を無償で課すケースが実態として存在しているのです。学生は事前に企業の評判や過去の実績を調べることが重要になるでしょう。
無償のインターンは違法?
「無給インターンシップは違法である」という言説を耳にすると、皆さんの中にはインターンシップの法的位置づけについて疑問を抱く方も多いことでしょう。事実として理解しておくべきは、全ての無給インターンシップが違法というわけではないということです。しかしながら、その内容によっては法律に抵触する可能性があるため、正しい知識を身につけることが皆さんにとって重要です。
無給インターンシップの違法性について耳にすると、「インターンシップでは報酬が得られるものなのだろうか」という疑問を持つ方も多いと思われます。
まず基本として認識していただきたいのは、無給のインターンシップそれ自体は違法ではないということです。インターンシップとは本来、学生が在学中に職業体験をする教育的プログラムです。学生が企業において就業体験を通じて、自らの将来のキャリアを熟考したり、実際の職場環境を理解するための機会となるため、無給であることがインターンシップの本質的な形態といえるのです。
インターンシップ活動が労働に当たるかどうかを見分ける際には、「企業からの指揮命令を受けているかどうか」という点が重要な判断材料となります。具体的には、以下のような条件に該当する場合を確認してみましょう。
- 会社から具体的な業務指示を受けている
- 他の従業員と同等の業務をこなす事が求められている
- 1日の拘束時間が長く、長期間におよんでいる
- 見学・体験型ではない
全体として見ますと、短期間で行われるインターンシップは労働者とみなされにくく、長期間続くインターンシップは労働者としての性格が強まる傾向があります。しかし皆さんが覚えておくべき重要なポイントは、インターンシップが実際に労働に該当するかどうかの判断は、先ほど説明した基準に照らして、その実際の活動内容から慎重に検討されるということです。

企業の利益になるような労働をさせる
企業が利益を得るような業務をインターン生にさせながら、実質的に労働力として活用しているにもかかわらず無給としている場合、これは法律違反になるということです。また、インターンシップの期間が長くなればなるほど労働力としての側面が強くなり、実際に行っている仕事内容が通常のアルバイトと区別できないケースも数多く見られます。
・企業の社員から指示を受けて調査活動を行う
・コピー取りやファイル整理といった事務作業を担当する
・電話での営業活動など企業の収益に直結するような実務を行う
このような労働を学生に求める場合は、正規の労働者と同様に適切な報酬を支払い、有給のインターンシップとして実施するべきだということをしっかり覚えておいてください。
過度な労働をさせる
決められた時間を超えて残業をさせられたり、長時間労働を強要されたりした場合は違法になる可能性があります。学生のやる気に付け込んで「社会人なら長時間労働は当たり前でしょ?」という雰囲気を作り、インターン生を酷使する企業には注意が必要です。入社後も同じ環境に置かれる可能性があるので、そういった企業を見つけたら避けるのが無難です。
有償であるとしても最低賃金以下である
たとえお給料が支払われていたとしても、それが最低賃金を下回っている場合は法律違反になるということです。例として考えてみましょう。東京都の企業で7時間働いて5,000円の報酬を得た場合、時給に換算すると714円になります。

無償のインターンを実施する場合の注意点とは

企業がインターンシップを実施する際は、適切な運営方法を理解しておく必要があります。インターンシップといっても1日体験型から長期実践型まで様々な種類があり、それぞれで法的な取り扱いが異なります。違法性を避け、学生にとって有意義な経験を提供するための重要なポイントを解説します。
インターンの目的を明確にする
学生に業務を担当してもらう目的が「労働力としての活用」なのか、それとも「職業体験を通じた企業理解の促進」という採用活動の一環なのか、この二つのどちらに当てはまるかをしっかり区別することです。もし労働力として業務を担当してもらうことが目的であれば、それがインターンシップという名称であっても、学生を労働者として適切に扱う必要があります。
雇用契約書を結ぶ
学生が労働者として認定される場合、企業側には労働条件の明示義務が発生します。具体的には、労働条件通知書または雇用契約書を作成し、学生へ交付する必要があります。「インターンシップやアルバイトの場合は契約書不要」という誤った認識が散見されますが、労働者性が認められる限り、学生であっても労働条件の通知は法的に必須です。
ハラスメントの対策を講じる
厚生労働省が公表した令和5年度職場ハラスメント実態調査によりますと、インターンシップに参加した学生の3割超がハラスメント被害を経験したという結果が示されています。このようなハラスメント事象は企業ブランドイメージの低下を招き、結果として採用活動にも負の影響を及ぼします。
企業経営上も様々なリスク要因となるハラスメントについては、体系的な対策の構築が不可欠です。具体的な防止策としては、学生との適切なコミュニケーション指針の策定と従業員研修の実施、並びにハラスメント行為発生時の懲戒処分や損害賠償責任の可能性について従業員の理解促進が重要となります。
もし違法な無償のインターンに参加してしまった場合の対処法

残念ながら違法な条件でのインターンシップに参加してしまった場合、適切な対処を行うことが重要です。一人で問題を抱え込まずに、周囲のサポートを受けながら解決策を模索しましょう。早期の対応により、被害を最小限に抑えることができます。
家族・友人など周りの人に相談する
まずは信頼できる家族や友人に相談することから始めましょう。客観的な意見を聞くことで、自分では気づかなかった問題点が明確になることがあります。寄り添ってくれて信頼できる人に相談することで、精神的な負担も軽減されるでしょう。
相談する際は、具体的な労働条件や業務内容を整理して説明することが大切です。証拠となる資料があれば一緒に確認してもらい、今後の対応策を検討しましょう。
学校のキャリアセンターに相談する
学校のキャリアセンターには、インターンシップに関する豊富なデータと経験があります。類似の事例やその解決方法について情報を持っている可能性が高いため、早めに相談することをおすすめします。キャリアセンターの職員は学生の就職活動をサポートする専門家であり、適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。

無償のインターンの魅力とは
ここまで無償インターンの法的な問題や注意点を中心に説明してきましたが、適切に運営される無償インターンには多くの魅力的な側面があります。給与が発生しないからこそ得られるメリットもあり、就職活動において有効に活用できる場面も多いのです。
責任を負わない
有償インターンの場合は給与を受け取る代わりに相応の責任が生じてきますが、無償インターンの場合はその責任が軽減されます。失敗を恐れずにチャレンジできる環境が整っているため、新しいことに積極的に取り組めるでしょう。
学習目的での参加が前提となるため、分からないことを質問しやすい雰囲気があります。社員の方々も教育的な観点でサポートしてくれることが多く、プレッシャーを感じることなく業務を体験できます。
短期間で業務を体験できる
無償インターンには1日完結型のものも多く、短期間でその業務について深く知ることができます。時間的な制約がある学生にとって、効率的に企業研究を進められる貴重な機会となるでしょう。
短期間だからこそ集中して取り組むことができ、限られた時間の中で最大限の学びを得られます。また、複数の企業のインターンに参加することで、比較検討も可能になります。
広い業界・職種を体験できる
近年は無償の短期インターンに力を入れている企業も増えてきており、幅広く業界・職種の理解を深められます。IT業界から金融業界、製造業からサービス業まで、さまざまな分野の企業がプログラムを提供しています。

無償のインターンをうまく活かすには!?
無償インターンの特徴を理解した上で、効果的に活用する戦略を立てることが重要です。ただ参加するだけでなく、明確な目的を持って取り組むことで就職活動における大きなアドバンテージを得ることができます。戦略的なアプローチについて詳しく解説します。
様々な業界に触れ自分との適性を知る
無償インターンの短期間という特性を活用して、多くの業界を経験しましょう。早い段階で幅広い業界に触れることで、自分の適性や興味を客観的に把握できます。
実際に現場を体験することで、業界研究だけでは分からない仕事の実態を知ることができます。想像していたイメージと現実のギャップを早期に発見し、より現実的なキャリア設計を行えるでしょう。
また、異なる業界の経験を通じて、自分の強みや弱みを多角的に分析できます。これらの気づきは、その後の就職活動における自己PRや志望動機の作成に大いに役立つはずです。
早期選考に呼ばれる可能性がある
無償の短期インターンであっても、早期選考の機会を提供する企業は数多く存在します。インターンでの取り組みが評価されれば、通常の選考プロセスよりも早い段階で内定獲得のチャンスを得られる可能性があります。
企業側としても、インターンを通じて学生の能力や人柄を直接確認できるため、優秀な参加者には積極的にアプローチしてきます。短期間でも真剣に取り組む姿勢を示すことで、企業に強い印象を残せるでしょう。
まとめ
無償インターンと有償インターンにはそれぞれ異なる特徴があり、参加目的に応じて適切に選択することが重要です。無償インターンは短期間で幅広い業務を体験でき、責任を負わずに学習に集中できる一方、有償インターンでは実践的なスキルを身につけながら収入を得ることができます。
適切に運営される無償インターンは、多様な業界を効率的に体験でき、早期選考のチャンスも得られる貴重な機会となります。自分の目的を明確にして戦略的に活用することで、就職活動における大きなアドバンテージを得ることができるでしょう。