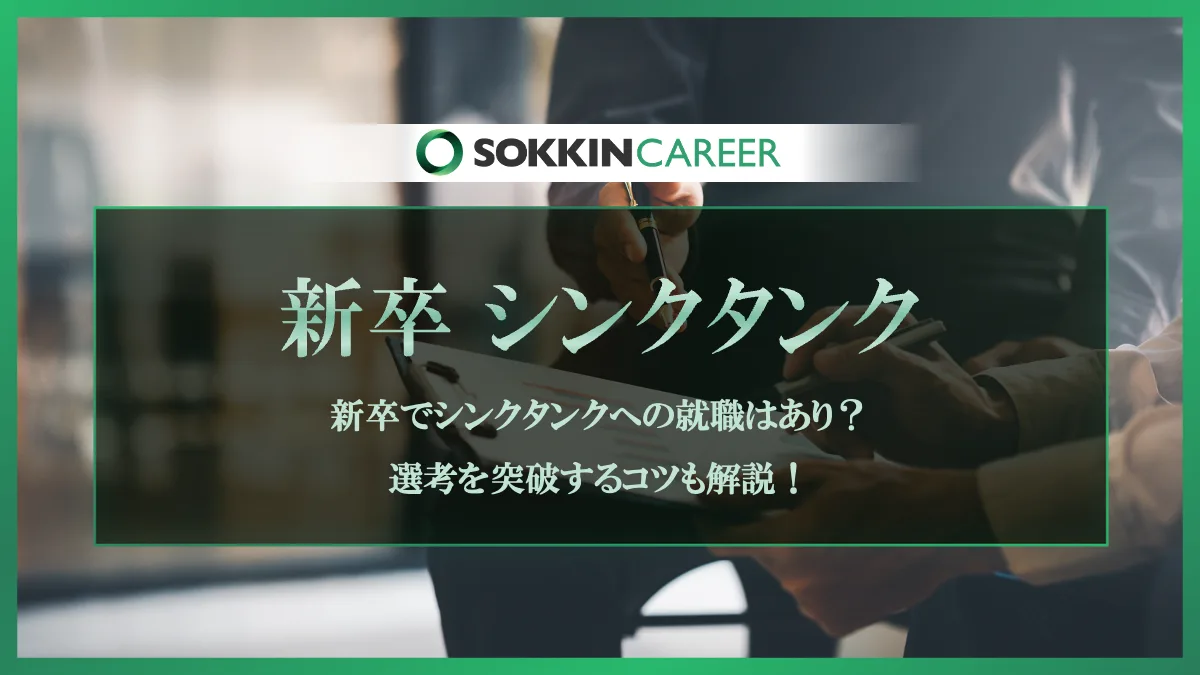新卒のなかには、卒業後の就職先としてシンクタンクを選択する人もいます。
しかしその一方で「シンクタンクではどういう業務をしているのかわからない」「シンクタンクへの就職を目指す際の難易度はどれくらいなのか」といった疑問・不安を抱えている人も少なくありません。
本記事ではシンクタンクへの就職を目指す新卒向けに、その全容を解説します。業務内容・向いている人の特徴・難易度なども含めて網羅的に紹介するので、ぜひ参考にしてください。
シンクタンクとは

シンクタンクとは、社会・経済・技術などさまざまな分野の専門家が集まって多角的な視点から調査・分析を行う研究機関です。別名「頭脳集団」とも呼ばれています。
シンクタンクは、単に情報を収集するだけではありません。その分析結果に基づいて特定の社会問題に対する政策提言や、企業経営に関する戦略の策定支援などを行います。
複雑な課題を深く掘り下げ、論理的に解決策を導き出さなければなりません。そのため高度な専門知識と分析能力、そしてそれを分かりやすく伝える力が重要です。
「政府系」と「民間系」のシンクタンクがある
政府系のシンクタンク
政府系シンクタンクは、各省庁の政策立案を支援する公的な研究機関です。
経済・社会・外交・科学技術・防衛といった多岐にわたる分野で、専門的な調査分析や研究を行うとともに客観的なデータや知見を提供します。これにより政府はより根拠に基づいた政策を形成し、国民の利益に資することが可能です。
民間系のシンクタンク
民間系シンクタンクは主に企業からの依頼を受けて、市場調査・経営戦略立案・新規事業開発支援などを行う営利目的の研究機関です。
金融機関やIT企業などのグループ会社であることが多く、各社の強みを活かした専門性の高いコンサルティングやシステム開発なども手掛けます。政府系と異なり、より実践的な課題解決や企業収益への貢献が求められる機関です。
シンクタンクの業務内容
シンクタンクの業務内容について確認していきましょう。
調査・分析
シンクタンクの主要な業務は、多岐にわたる社会や経済の課題に関する調査・分析です。具体的には、以下のような業務があげられます。
・文献調査
・アンケート調査
・ヒアリング
・現状の把握
・問題点の特定
例えば人口動態の予測・景気動向の分析・産業構造の変化・特定の政策が社会に与える影響の評価などは、シンクタンクの業務の一部です。
これらの調査結果をもとに論理的かつ客観的な視点から詳細なレポートを作成し、政策提言や未来予測のための根拠となる知見を提供します。

コンサルティング
コンサルティングも、シンクタンクが行う業務のひとつです。クライアントが抱える具体的な課題に対し、調査・分析で培った専門知識や知見を活かして解決策を提案し、その実行を支援します。
シンクタンクのコンサルティング業務は、単なる情報提供に留まりません。具体的な業務内容として、以下のようなものがあげられるでしょう。
・新規事業開発
・業務プロセス改善
・ITシステム導入支援
クライアントのニーズを深く理解し、データに基づいた論理的な解決策を提示しなければなりません。さらに解決策が現場で機能するようにアクションプランの策定から実行支援まで一貫して伴走することで、クライアントの持続的な成長に貢献します。
シンクタンクとコンサルティングファームの違い
シンクタンクとコンサルティングファームは、ともに専門知識を活かして課題解決に貢献する組織です。しかし、その目的やアプローチに明確な違いがあります。
シンクタンクの主な役割は「調査・研究」と「政策提言」です。政府系であれば社会全体の課題、民間系であれば産業や経済の動向などがあげられます。幅広いテーマについて長期的な視点で深く分析し、その結果を報告書や提言として公表することが主な業務内容です。公共性や学術性が重視されることが多く、客観的な知見や未来予測を提供します。社会や企業の意思決定に影響を与えることを目指すのが、シンクタンクの役割といえるでしょう。
一方でコンサルティングファームの主な役割は、クライアントが抱える具体的な経営課題の「解決策提案」と「実行支援」です。短期間で成果を出すことが求められるケースが少なくありません。戦略策定からITシステム導入まで、多岐にわたる分野で実践的なコンサルティングを行います。一気通貫のサポートで、直接的な企業価値向上に貢献するケースが多いでしょう。

新卒でシンクタンクに就職することの魅力

新卒でシンクタンクに就職する魅力を確認していきましょう。
規模が大きい仕事を行える
シンクタンクで働く大きな魅力のひとつは、社会や経済に大きな影響を与える大規模な仕事に携われる点です。
政府系のシンクタンクであれば、国の政策立案に直接関われます。国民生活全体に影響を及ぼすようなプロジェクトに貢献できる点は、魅力といえるでしょう。
民間系シンクタンクの場合、大手企業の事業戦略・新規事業開発・特定の産業全体の動向分析などを行います。シンクタンクの規模によっては、広範囲にわたる重要な意思決定をサポートする機会が豊富です。個社の枠を超えて社会全体や産業構造といったマクロな視点から課題解決に取り組めるため、仕事のスケール感と社会貢献性を強く感じられるでしょう。
成長できる環境で働ける
新卒でシンクタンクに就職する魅力は、知的好奇心を刺激される環境で大きく成長できる点です。
多様な分野の最先端テーマに取り組むため、常に新しい知識を吸収して深い専門性を追求する機会に恵まれます。複雑な課題を論理的に分析して解決策を導き出す思考力や、多角的な視点から物事を捉える力が養われるでしょう。経験豊富な研究員やコンサルタントと共に働くことで、実践的なスキルや高度な専門知識を効率的に習得できます。
転職に有利である
新卒でシンクタンクに就職する魅力は、その後のキャリアパスが広がり、転職市場において非常に有利である点です。
シンクタンクでは、以下のような高度なスキルが培われます。
・論理的思考力
・問題解決能力
・多様な業界やテーマに関する専門知識
これらは、あらゆる企業で高く評価されるスキルです。特に複雑な課題を構造化してデータに基づいて解決策を導き出す経験は、以下のような職種で即戦力として役に立ちます。
・経営戦略部門
・金融機関の調査部門
・ほかのコンサルティングファーム

新卒でシンクタンクに向いている人の特徴
新卒でシンクタンクに向いている人の特徴を紹介します。
知的好奇心がある
新卒でシンクタンクに向いている人の特徴のひとつとして、尽きない知的好奇心を持っていることがあげられるでしょう。
シンクタンクの業務は常に新しい社会課題や未解明なテーマに向き合い、その本質を深く探求することの連続です。経済・社会・科学技術など多岐にわたる分野で、「なぜそうなるのか」「どうすれば解決できるのか」といった問いを持ち続けなければなりません。さらにその問いに対して積極的に調べ、考え抜く姿勢も不可欠です。
課題解決力に長けている
新卒でシンクタンクに向いている人の特徴として、優れた課題解決能力を持っていることもあげられます。
シンクタンクの業務では複雑で多岐にわたる社会や企業の課題に対し、その根本原因を特定して論理的かつ実践的な解決策を導き出さなければなりません。目の前の情報を鵜呑みにせず、様々な角度から検証して筋道を立てて思考できる力が必要です。与えられた問いだけでなく、真の課題は何かを見極める能力も求められます。
コミュニケーション力がある
優れたコミュニケーション能力を持っていることも、新卒でシンクタンクに向いている人の特徴といえます。
シンクタンクの業務ではクライアントや社内外の専門家、多様なバックグラウンドを持つチームメンバーと円滑に連携することが不可欠です。複雑な情報を正確に理解し、自身の考えを明確かつ論理的に伝える能力が求められます。また、相手の意見に耳を傾け、協力しながらプロジェクトを進める協調性も重要です。
プレゼンテーションが上手い
優れたプレゼンテーション能力を持っていることも、新卒でシンクタンクに向いている人の特徴としてあげられます。
シンクタンクの業務では調査分析で得られた複雑な情報や練り上げた提言を、クライアントや関係者に説得力をもって分かりやすく伝えることが不可欠です。どんなに素晴らしい分析結果も、効果的に伝えられなければ意味がありません。聴衆の関心を引きつけて理解を深めてもらうための構成力や表現力は、シンクタンクで成果を出すうえで非常に重要です。
専門知識がある
新卒でシンクタンクに向いている人の特徴は、特定の分野における専門知識を持っていることです。
大学や大学院で培った専門分野における深い知識は、シンクタンクが扱う多岐にわたるテーマの調査・分析において大きな強みとなります。既存の知見を体系的に理解し、それを基盤として新たな知見や提言を生み出す力が不可欠です。
業務に必要な専門知識は、入社後のOJTや学習でさらに深められます。しかし確かな基礎があることで、より早く第一線で活躍できるでしょう。

新卒でシンクタンクの就職が難しい理由
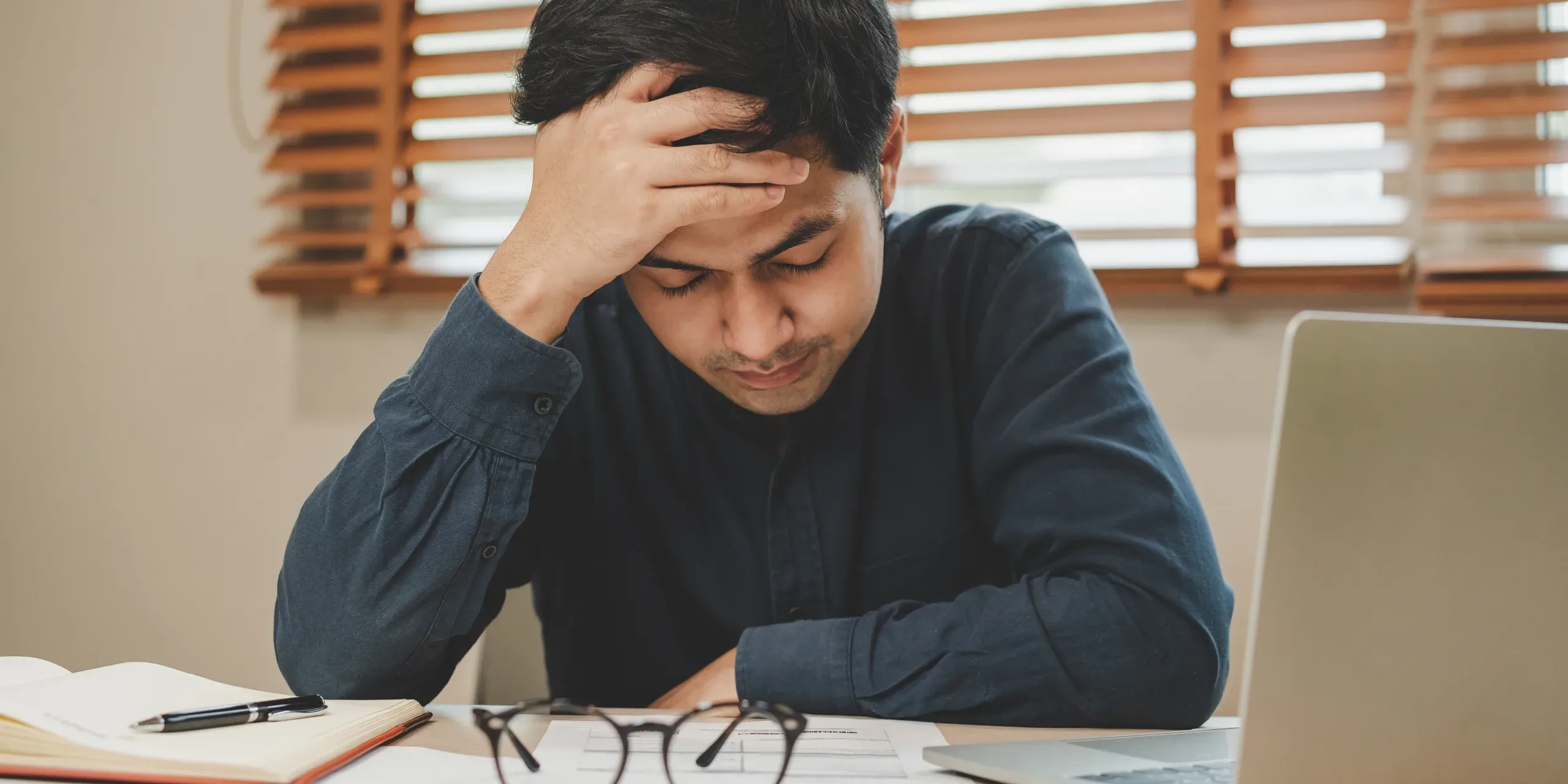
新卒でシンクタンクへの就職が難しい理由を紹介します。
採用人数が少なく高い倍率になりやすい
新卒でシンクタンクへの就職が難しい理由として、高い倍率になりやすい点があげられるでしょう。シンクタンクの種類に限らず、採用人数が限られているからです。
多くのシンクタンクは少数精鋭で業務を行っており、毎年募集される新卒の枠は非常に少ない傾向にあります。一方で社会貢献性の高さや知的な専門性への魅力から、多くの学生が応募するケースは少なくありません。その結果、必然的に競争倍率が高くなります。
高学歴志向である
採用において高い学歴を重視する傾向が強い点も、新卒でシンクタンクへの就職が難しい理由のひとつです。
シンクタンクは、専門的な調査・研究を通じて、複雑な社会課題や経済問題に対する深い分析と論理的な提言を行わなければなりません。そのため、高度な思考力・分析能力・知的な探究心を持つ人材を求めています。
その素養を測る指標のひとつとされているのが、国内外の難関大学や大学院の出身者か否かです。高いレベルの学習環境で培われた基礎学力や専門知識を重視する、というシンクタンクの特性が背景にあります。
選考内容のレベルが高い
選考内容のレベルが非常に高い点も、新卒でシンクタンクへの就職が難しい理由のひとつでしょう。
シンクタンクでは論理的思考力や分析能力を深く問われるケーススタディや、高度な専門知識を要する筆記試験が課されることが多い傾向にあります。また自身の研究テーマや知的好奇心の深さを問う面接など、思考のプロセスや問題解決へのアプローチが厳しく評価されます。

新卒でシンクタンクに就職するためのポイント
新卒でシンクタンクに就職するためのポイントを紹介します。
ESに力を入れる
新卒でシンクタンクに就職するためのポイントとして、ESに力を入れることは重要です。
・志望動機の根拠
・入社後のイメージ
上記3つにフォーカスして、解説します。
コンサルティングの違いを明確にする
ESを作成する際の重要なポイントは、コンサルティングファームとの違いを明確に意識してシンクタンク特有の魅力にフォーカスすることです。
シンクタンクは、短期的な企業課題解決にとどまりません。社会全体の動向・政策・学術的な探究を通して長期的な視点で知を創造し、提言を行う役割を担います。
ESでは、「なぜ個別の企業の利益追求ではなく、より広範な社会や公共への貢献に関心があるのか」「なぜ深い調査研究や知的な探求に価値を見出すのか」といった点を具体的に示しましょう。シンクタンクへの強い志望度と適性をアピールできます。
志望動機の根拠をしっかりと書く
ESを作成する際、志望動機の根拠を具体的に示すことは非常に重要です。シンクタンクで働きたい理由、その背景となる興味関心などを明確に記述しましょう。体験や学業での学びといった、具体的なエピソードを交えることで説得力が増します。
入社後のイメージを伝える
ESを作成する際、入社後の具体的なイメージを伝えることは熱意と適性を示すうえで効果的です。
具体的なビジョンを示すことで、企業側は応募者がシンクタンクの業務内容を深く理解していると判断できます。
漠然とした目標ではなく、シンクタンクの専門性や公共性といった特性を踏まえましょう。自分がどのように貢献できるのかを具体的にイメージして記述することで、説得力が増して企業への強い入社意欲をアピールできます。
適性検査の対策を怠らない
新卒でシンクタンクに就職するための重要なポイントは、適性検査の対策を徹底することです。
シンクタンクの選考では、SPIや玉手箱といった一般的な能力検査だけではありません。論理的思考力や地頭の良さを測るため、独自のケース問題や小論文が課されることがあります。これらの検査は単なる知識を問うだけでなく、複雑な情報を素早く正確に処理して論理的に思考する能力が不可欠です。
資格やスキルで差別化する
新卒でシンクタンクに就職するためのポイントとして、資格やスキルで差別化を図ることもあげられます。
特定の業界やテーマに関する専門的な知識を習得しておくことで、ほかの候補者との差別化が可能です。
専門的な知識・スキルは入社後に即戦力として活躍できる可能性を示し、学習意欲や専門性をアピールする強力な材料にもなります。大学での研究活動や独学を通じて積極的に習得し、ESや面接で具体的なエピソードとともに伝えましょう。
大企業以外も受ける
新卒でシンクタンクに就職するためのポイントとして、大手シンクタンク以外にも目を向けることがあげられます。
中堅・小規模のシンクタンクは、特定の分野で高い専門性を持っていたり、ユニークな研究テーマに取り組んでいたりするケースが少なくありません。
採用人数は大企業と比較すると少ない場合が多いでしょう。しかし一人ひとりの業務範囲が広く、裁量を持って働ける環境であることが多い傾向にあります。

新卒におすすめのシンクタンクの大手企業

新卒におすすめのシンクタンクの大手企業を紹介するので、参考にしてください。
野村総合研究所
野村総合研究所は、日本を代表する大手シンクタンク兼ITソリューション企業です。
コンサルティングとITソリューションを融合した独自のビジネスモデルが強みで、企業戦略からITシステム構築まで一貫したサービスを提供しています。
日本総合研究所
日本総合研究所は、三井住友フィナンシャルグループの中核を担うシンクタンクです。
国内外の経済・社会・産業に関する調査分析から、企業や公共機関への経営戦略・IT戦略のコンサルティング、さらには新規事業の創出まで幅広く手掛けています。
NTTデータ経営研究所
NTTデータ経営研究所は、NTTデータグループの戦略系シンクタンクです。
ITに関する深いノウハウを強みに中央省庁や地方自治体への政策提言といった、社会性の高い大規模プロジェクトを数多く手掛けています。
三菱総合研究所
三菱総合研究所は、日本の社会・経済・科学技術など幅広い分野で政策提言、コンサルティングを提供する大手総合シンクタンクです。
三菱グループの総合力を背景に地球規模の課題から地域社会の課題まで、多岐にわたるテーマに深く関与しています。
みずほリサーチ&テクノロジーズ
みずほリサーチ&テクノロジーズは、みずほフィナンシャルグループのシンクタンクです。
経済・金融の専門性を基盤に社会や産業の課題解決に貢献する調査研究や政策提言を行うほか、企業の経営戦略支援やDX推進も手掛けています。

シンクタンクと同時に狙ってもいい業界
シンクタンクと同時に狙うべき業界を確認していきましょう。
コンサルティング業界
シンクタンクと同時に検討すべき業界として、コンサルティング業界があげられます。
コンサルティングファームは企業や行政が抱える複雑な課題に対し、定量・定性の両面から深く分析して最適な戦略や業務改善策を提案・実行支援することが業務です。これは、シンクタンクが政策や社会課題に対して調査・提言を行う役割やアプローチと極めて似ています。
特に戦略系コンサルティングファームは、国の産業構造やマクロ経済に関わる大規模プロジェクトも少なくありません。
IT業界
シンクタンクと並行してIT業界も視野に入れるべきです。
特にSIerやITコンサルは、行政機関や大手企業の複雑な業務プロセスに入り込んで技術的・構造的な課題解決に取り組みます。これは、シンクタンクが行う政策提言や業務改革支援と極めて近いアプローチです。
現代のシンクタンクの多くはビッグデータ分析・AIを活用したシミュレーションなど、IT技術を用いた高度な調査分析を行っています。IT業界との連携は、シンクタンクの業務を進めるうえで不可欠です。
金融業界
シンクタンクと同時に金融業界も有力な選択肢です。
特に金融機関のリサーチ部門や調査部門は、経済全体の動向・産業構造・企業活動を深く分析して投資戦略や経営判断を支援します。これは、シンクタンクが社会や経済の複雑な構造を分析して課題解決のための知見を提供する役割と共通しています。
まとめ
新卒のシンクタンク就職事情について解説しました。
汎用性の高い知識・スキルの習得が可能なシンクタンクは、新卒からの人気も高い傾向にあります。しかし採用枠はあまり多くなく、就職するためには徹底した事前準備が欠かせません。
本記事では、向いている人の特徴・難しい理由・就職するためのポイントなども紹介しました。これらを参考にして視野を広げた就職活動を行い、希望する業界への採用を目指してください。