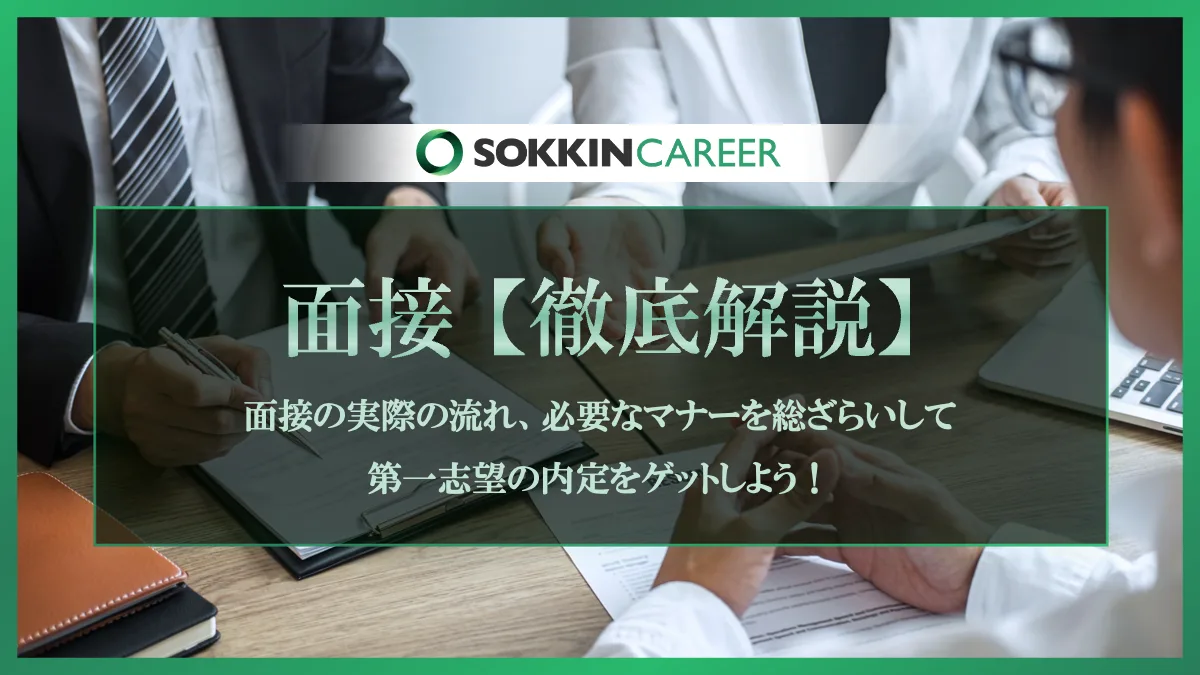就職活動において面接はマナーから質問内容まで多くのことに神経を使う大変な場面です。
基本マナーや言葉遣い、面接官の質問にどう答えるかなど、1つ1つを丁寧に確認して、どれだけミスを減らせるかが重要になってくるでしょう。
この記事では、第一志望の内定を獲得するための面接対策について詳しく解説しています。
服装や持ち物などの事前準備から面接当日の流れ、面接官から聞かれる質問の詳細や答え方などを具体的に解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
- 【対面の場合】面接前にどんな準備をしておく?
- 【Web面接の場合】面接前にどんな準備をしておく?
- 面接当日!実際に面接が始まるまでをシミュレーションしよう
- 面接はどんな流れで進む?実際の流れをチェック!
- 【コラム】就活全体で面接は何回ある?
- 面接で聞かれる質問にはどんな意図がある?
- 【シーン別】よくある質問を流れごとにチェックして対策しよう!
- 【コラム】一次と最終で質問内容はどれだけ変わる?
- 実際に回答するときのポイント4選を解説!
- 逆質問はどうするのが正解?ポイント3つを徹底解説!
- 【コラム】面接で答えに詰まってしまったとき、あなたならどうする?
- 面接前後、電話やメールの連絡はどうするのが正解?
- 面接にどうしても受からない…その原因と対策をチェックしてみよう
- まとめ
【対面の場合】面接前にどんな準備をしておく?

面接前にしておく事前準備について見ていきましょう。
これから受ける面接が対面なのかWebなのかしっかりと確認したうえで適切な準備を行いましょう。
まず、対面の場合の面接前の準備について以下で詳しく解説します。
①面接場所、時間を確認し当日の予定を立てよう
まずは面接場所、時間を確認し当日の予定を立てましょう。当日に道に迷ったり遅刻したりすると、それだけで大きなマイナス評価につながってしまいます。
事前に面接会場の住所を確認し、最寄り駅からのルートを調べておきましょう。できれば面接前日までに現地まで足を運んで、実際の所要時間を確認しておくと安心です。
②必要な持ち物は前日朝には要チェック!
面接当日に慌てて準備することがないように、必要な持ち物は前日までにチェックしておきましょう。
面接に必要な持ち物は以下のようなものです。
- 履歴書のコピー
- 求人情報や会社案内のコピー
- 応募先企業の連絡先、面接会場の地図など
- 筆記用具
- 現金
- スマートフォン
以下は、必須ではありませんが、必要に応じて持っていくと便利です。
- 手鏡
- 腕時計
- エチケット用品
- 折りたたみ傘
- モバイルバッテリー
- 常備薬
③面接に適した服装・カバンにしよう
面接では第一印象が非常に重要なので、面接に適した服装とカバンを選ぶことが大切です。
面接に適した服装の選び方は、基本的には「清潔感」「誠実さ」を重視して選び、迷ったら「無難な」選択をするとよいでしょう。

応募先の企業から指定がない場合はスーツが基本です。黒系や濃いグレーや紺色で、柄のない無地のものが無難です。
ネクタイの色は紺色かグレー、エンジ色など落ち着いたカラーでストライプまたは無地のものを選びましょう。
足元は男性の場合は黒の革靴、女性は黒のシンプルなパンプスが基本です。靴下も派手な柄は避けて黒や紺の無地のものを選びましょう。
カバンについては、A4サイズの書類が入る黒や濃いグレーなど落ち着いた色のビジネスバッグで、スーツと統一感があり清潔感のあるものを選びましょう。面接中は椅子の横に置くか立てかけますので、自立するタイプのものがおすすめです。
面接官は面接の受け答えだけでなく、身だしなみからも社会人としての基本が備わっているかを見ています。服装やカバンも面接の前日までにしっかりと準備して、少しでも印象が良くなるようにしましょう。
【Web面接の場合】面接前にどんな準備をしておく?

次に、Web面接の場合の準備について解説します。
Web面接では服装だけでなく、面接に使うツールやネット環境などの準備が必要ですが、慣れていないと時間がかかる場合もあります。
以下でWeb面接の事前準備について解説します。
①服装チェックなどは対面と同様にやろう
服装チェックなどは対面と同様にやりましょう。画面越しのWEB面接だからといって、服装への配慮を怠らないよう注意が必要です。
WEB面接は自宅で受けることが多いですが、自宅でもスーツに着替えて髪型や身だしなみも対面面接と全く同じレベルで徹底しておく必要があります。また、画面に映る上半身だけでなく、全身の身だしなみを整えるようにしましょう。
②面接媒体を絶対に確認!
面接媒体は企業によってZoom、Google Meet、Teamsなど多岐にわたるため、必ず事前にチェックすることが大切です。
企業からどのツールを使用するか指定がありますので、面接媒体のソフトを事前にダウンロードし、アカウントの設定を完了させておきます。
③インターネットの接続が十分か確認しておこう
インターネットの接続が十分か確認しておくことも大切です。
接続が不安定だと、音声や映像が途切れて面接の進行に支障が出てしまう可能性がありますので注意しましょう。


④実際に使うデバイスも事前に要チェック!
実際に使うデバイスも事前にチェックしておきましょう。
まず、ビデオ通話で使用するパソコンなどのカメラとマイクの動作確認を行いましょう。カメラの角度や画質、マイクの音質をチェックし、外付けのWebカメラやヘッドセットが必要かどうかを早いうちに判断しておくことが大切です。
面接当日!実際に面接が始まるまでをシミュレーションしよう

面接当日は余裕を持って行動し、自分の実力が十分に発揮できるようにすることが重要です。
以下で面接開始前にできる直前の準備やシミュレーションについて解説します。
①時間に余裕を持って現地に到着しておこう
面接当日は想定外のアクシデントに備えて余裕を持って行動しましょう。
特に、遅刻を避けるために、時間に余裕を持って前日に立てたスケジュール通りに行動して現地に到着しておくことが大切です。
たとえば、電車が遅延したり、駅の出口を間違えたり、途中で道に迷ったり、急な体調不良など、予想外の原因で時間を取られることがあります。目安として面接開始時間の30分前には最寄り駅に到着し、10分前には受付に向かうというスケジュールを組みましょう。
②受付から好印象を持たれるようにしよう
面接は受付の瞬間から始まっていると考えましょう。応募する企業にもよりますが、受付のやり取りも評価の対象になる場合があります。
時間の目安としては、面接開始の5分前には受付を済ませておくようにします。開始時間ギリギリになるのは印象が悪くなりますし、早すぎるのもよくないため注意してください。
③入室!マナーを意識して挨拶しよう
入室時のマナーは面接の第一印象を大きく左右するため重要です。マナーを意識して礼儀正しく挨拶することで、良い印象を与えることができれば、その後の面接もスムーズに進みやすくなります。
入室の流れは以下のようになります。
- ドアを3回ノックする
- 入室したら面接官にお辞儀する
- 着席を促されたら椅子に座る
ビジネスではノックの回数は3回が基本です。ドアをノックすると面接官から「どうぞ」と入室を促されますので、その返事を聞いてから「失礼いたします」と言って入室してください。
入室後は、ドアを静かに閉め面接官の方を向いてお辞儀します。
椅子の横に立ってから「本日はお時間をいただき、ありがとうございます。○○大学の○○と申します。よろしくお願いいたします」と挨拶しましょう。
その後、面接官から着席するよう言われたら、再度お辞儀をしてから座るようにします。
【Webの場合】事前にサイトに入室、挨拶はハキハキと丁寧にしよう
WEB面接では、面接開始時間の5分前には、指定されたサイトに入室しておきましょう。早めに入室することで、証明やカメラの調整が必要な場合に対処できますし、身だしなみを整える余裕も出ます。
また、カメラのレンズを見て話すことで、面接官と目を合わせているような印象を与えることができます。WEB面接でも、カメラを通じたアイコンタクトを意識して話しましょう。
面接はどんな流れで進む?実際の流れをチェック!

面接本番がどのような流れで進んでいくのか知っておくことで、事前準備やシミュレーションがしやすくなり、本番でも落ち着いて対応できるようになります。
一般的な面接の流れは以下のように進みます。
- 自己紹介
- 志望動機
- 自己PR
- 逆質問
- 退室
以下で面接の実際の流れをより具体的に紹介しますのでしっかりと確認しておきましょう。
①自己紹介
面接の冒頭では、ほぼ確実に自己紹介を求められます。
自己紹介では、大学名、学部・学科、氏名を簡潔に述べることが基本です。
「○○(氏名)と申します」の名乗りに続いて「本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます」というように、感謝の気持ちを伝えることも重要です。
②志望動機
志望動機は、入社意欲や熱意があるか、早期退職しないかといった点が確認されています。なぜその企業を選んだのか、どのような点に魅力を感じているのかを具体的に説明しましょう。


③自己PR
自己PRは自分の強みや能力を面接官にアピールできるチャンスです。あらかじめ自己分析で自分の強みや性格の特徴を把握しておき、入社後の業務に関係があるものをセールスポイントとしてアピールしましょう。
面接官は、応募者が採用後に自社で活躍できる人材なのかを判断する際に自己PRの内容も大いに参考にしています。応募している業務内容に関係のある強みを選んで、過去の具体的なエピソードを交えて分かりやすく伝えると印象に残りやすくなります。
④逆質問
逆質問は、面接の終盤で「何か質問はありますか?」と聞かれる場面です。どのような質問をするかによって志望意欲や意気込みをアピールするチャンスとなります。「特に質問はありません」と答えないようにしましょう。
良い逆質問をするためには、事前に企業研究や業界研究をしっかりと行うことが重要です。業界に高い関心がないと出てこないような疑問点や、長く働く意欲や熱意があるからこそ出てくる質問をすることで志望度の高さが伝わります。
⑤退室
面接の最後は退室のマナーを徹底しましょう。面接が終了したからといって気を抜かず、最後まで丁寧な対応をすることで良い印象を残すことができます。
退室時の流れは以下のようになります。
- 椅子から立ちお礼を伝える
- ドアの前で面接官に挨拶をする
- 退室する
面接官から面接終了と伝えられたら、椅子から立ち上がり、「本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき、ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えましょう。
ドアの前までゆっくりと歩き、最後にもう一度面接官の方へ向き、「ありがとうございました」と挨拶してからドアを開け、静かに退室します。ドアを閉める際は、大きな音を立てないよう丁寧に閉めることが大切です。
【コラム】就活全体で面接は何回ある?

就職活動全体を通した面接は、主に一次面接、二次面接、最終面接という流れで進められます。一般的には2〜4回の面接を実施する企業が多いです。
面接の回数ごとに質問内容や求められる回答が変化しますので、それぞれの面接のポイントを確認しておきましょう。
一次面接は基本的な人柄や受け答え、志望動機の確認が主な目的のため、通過率は高めになります。ポイントは清潔感や話し方、態度やマナーに気を付けて、良好な第一印象を目指しましょう。
二次面接は業務に対する適性や将来性の見極めが行われます。実務で活躍できる人材か、チームでの業務に馴染めるかといった点が確認されるため、過去のエピソードも交えて効果的な自己PRを考えましょう。
最終面接は合否の判断が行われるため、部長や役員、社長などが面接官になることが多いのが特徴です。志望度の高さ、価値観や人間性が合うかどうかの確認が行われ、自社で長く活躍できる人材かがチェックされます。
それぞれの目的を理解したうえで、面接の段階に応じた対策を行いましょう。
面接で聞かれる質問にはどんな意図がある?

面接で聞かれる質問にはどんな意図があるのか見ていきましょう。
面接官の質問には明確な意図や目的がありますので、その意図を理解して適切な回答をすることが大切です。
①学生の志望度、熱意のチェック
第一に、企業が重視するのは応募者がどの程度自社を志望しているかという点です。
志望度の高さは、入社後のモチベーションや勤務態度、同僚や上司との関係性に大きく影響するため、多くの企業がこの点を優先的にチェックします。
②経験やスキル、どのように活躍できる人材かのチェック
次に、経験やスキル、どのように活躍できる人材なのかをチェックしています。
応募者がどのように活躍できるかは、採用後に社内でどのように人材を活用するのかを左右する重要な要素です。特に理系のITや建築などの専門分野を仕事とする企業は、専門知識の有無やスキルについて非常に敏感になるため、こちらを優先的に確認する企業も多いです。
③志望者の人格、求めている人物像かのチェック
応募者が自社の社内文化や価値観とマッチしているかも重要です。優秀なスキルを持っていても、社内の雰囲気に馴染めない人は長期的に活躍が期待できないからです。
たとえば、「あなたは周りからどのような人だと思われていますか?」といった質問から、応募者の人格や人柄などの人物像を判断して、自社と合うかをチェックしています。


④自社で長く働けるかをチェック
自社で長く働ける人物かをチェックしたいという意図もあります。
最近は転職が一般的になっていることもあり、長期的に活躍してくれる志望度の高い人材を求める企業が多くなっています。採用や教育にはコストがかかりますので、早期退職のリスクが低く、長く定着する人材が評価されやすくなっています。
【シーン別】よくある質問を流れごとにチェックして対策しよう!

自己紹介や志望動機など、面接の流れごとによく聞かれる質問があります。面接のシーンごとにどのような質問があるのかチェックして対策しておきましょう。
以下で一般的によく聞かれる質問を解説しますので、回答については志望する企業の特徴や求める人材像に合わせて考えることをおすすめします。
①自己紹介などでされる質問
面接の冒頭では自己紹介を求められます。その際は以下のような質問になることが多いです。
- 「自己紹介をしてください」
- 「30秒で(1分間でなど)自己紹介をしてください」
- 「あなたの特徴について教えてください」
こういった質問は、面接官が応募者の基本情報について確認するとともに、緊張をほぐすためのアイスブレイクの役割もあります。
②志望動機などでされる質問
志望動機は、企業への志望度や理解度を確認するための質問です。
- 「志望動機を教えてください」
- 「なぜこの業界を志望しているのですか?」
- 「弊社は第一志望ですか?」
- 「なぜ他社ではなく弊社を志望しているのですか?」
応募する企業だけでなく、他社との比較や業界全体の理解、志望業界と他の業界との違いなども含めて幅広く研究しておきましょう。
③自己PRなどでされる質問
自己PRを求める理由は、応募者の強みやセールスポイント、能力を確認するためです。
- 「あなたの強みを教えてください。」
- 「これまでの経験の中で、特にアピールできることは何ですか?」
- 「入社後に活かせる、あなたならではの強みは何だと思いますか?」
- 「まわりの人から、どんな人だと言われますか?」
④逆質問などの面接終盤でされる質問
面接の終盤で企業への関心度や意欲を確認するために以下のような逆質問があります。
- 「何か質問はありますか?」
- 「最後に一言ありますか?」
- 「何か言い残したことはありますか?」
逆質問では、企業文化について気になることや、企業研究や業界研究で深く調べても分からなかった不明点について質問するとよいでしょう。その会社での将来のキャリアパスについて質問するのも、長期的な成長意欲が伝わるため好印象になります。
また、「最後に一言」を求められたときは、あらためて入社への強い意欲と意気込みを伝えるとよいでしょう。
【コラム】一次と最終で質問内容はどれだけ変わる?

面接の段階によって、質問の内容や深さは大きく変わります。
一次では、主に基本的な適性や人柄、社会人としての基本マナーなどが見られています。最終面接では入社の意志や志望度の高さ、企業との相性、将来性などが見られています。
たとえば、一次面接では以下のような質問が多いです。
- 「自己紹介をお願いします」
- 「学生時代に力を入れたことは何ですか?」
- 「当社を志望した理由は何ですか?」
- 「あなたの長所と短所について教えてください」
- 「これまでのアルバイトや部活での経験を教えてください」


- 「他社ではなく当社を志望したのはなぜですか?」
- 「入社後に実現したいことはありますか?」
- 「10年後にどのようなキャリアを目指していますか?」
- 「当社の事業をどのように成長させていきたいですか?」
このように、面接の段階に応じて求められる回答の質や深さが変化するため、それぞれの面接の目的を理解し、適切な準備を行うことが重要です。
実際に回答するときのポイント4選を解説!

面接で良い回答をするためには、内容だけでなく話し方や伝え方も重要です。
以下で解答するときの4つのポイントを解説しますので参考にしてください。
①相手の目を見て、自信を持って話す
面接に限った話ではありませんが、相手の目を見て話すことはコミュニケーションの基本です。目を見て話すことで、自分の表情や話すときの熱意をより鮮明に伝えることができます。
相手の目を見ることで、面接官の反応を確認しながら話すことができるため、自分自身も話しやすくなります。面接官が興味を持ってくれている様子であれば、その話題をさらに詳しく説明しやすくなります。逆に、理解が難しそうであれば、より分かりやすい表現に変えたりするなど、相手に合わせた対応ができるようになるでしょう。
また、自信を持って話すことも重要です。たとえ緊張していても、背筋を伸ばしてはっきりとした声で話すことで、誠実な印象となり、コミュニケーション能力を評価してもらえるようになります。
②結論ファースト、要点を絞ってわかりやすく伝える
面接では「結論ファースト」の話し方を心がけましょう。
最初に短い文章で言い切る形で結論を分かりやすく述べてから、続いてその理由や根拠となる具体例を説明するという流れを意識することが大切です。
このような話し方をすることで、最初に伝えたいことが明確になり、その後の説明をより理解しやすくなります。
また、要点を絞り、簡潔で分かりやすい説明を心がけましょう。長すぎる回答は聞き手の集中力が落ちてしまい、マイナスの印象を与えてしまう可能性がありますので注意してください。
③面接官の質問意図をしっかり理解する
面接官の質問には必ず明確な意図があります。その意図を正確に読み取り、的確に答えることで、面接官からの評価を向上させることができます。
たとえば、「学生時代に最も力を入れたことは何ですか?」といった質問では、単に活動内容を知りたいのではなく、過去の経験から、人柄や能力、内面的な特徴や課題への取り組み方を知りたいという意図があります。
④客観的事実、数値などの情報を積極的に使う
主観的な感想ではなく、客観的な事実や数値を用いることで、自分のスキルや実績に説得力を持たせることができます。
たとえば、「継続的にコツコツ努力できる」ことをアピールするときは、「毎日30分の勉強を1年間続け、合格率20%以下の資格を取得することができました」というように、具体的な数値や成果を交えて話しましょう。
そうすると、単に「努力しました」という主観的な表現と比較して、アピールしたいポイントが明確になり、面接官にとって評価しやすい内容になります。
逆質問はどうするのが正解?ポイント3つを徹底解説!

逆質問とは、面接の終盤で面接官から「何か質問はありますか?」と聞かれる場面のことです。
逆質問はどうすればよいのか、おさえておきたい3つのポイントを解説します。
①相手がどうして逆質問するのかを理解する
逆質問でどんな質問をするか考えるときは、面接官がどうして逆質問をするのか、その理由を理解することが重要です。
面接官が逆質問をするのは、以下のように複数の理由があります。
- 志望度の高さを見極める
- 業務や業界に対する理解度を確認するため
- コミュニケーション力をチェックする
まず、応募者からの質問内容によって自社で働くことや募集している職種に対する志望度の高さをチェックしています。実際に働くことを前提とした具体的な質問があると、それだけ関心が高く、志望度も高いと評価されます。ミスマッチや早期退職のリスクも下がるため、積極的に採用を検討すべき人材と判断されるでしょう。
また、逆質問の内容から自社での業務や業界全体に対する理解度も予測することができます。業界特有の事情に関わる深い質問が出れば、それだけ業界研究や企業研究のレベルが高いと考えられます。
また、これまでの面接の会話の流れを踏まえた適切な質問ができるか、といった点からコミュニケーション力や論理的な思考力なども評価されています。
②逆質問するときのマナー、気をつけることを意識する
逆質問をする際にも、基本的なマナーを守ることが重要です。
逆質問で企業のホームページや採用情報で簡単に調べられる基本的な情報について質問するのも適切ではありません。たとえば「御社の事業内容を教えてください」といった質問は避け、事前に調べられる情報は自分で調べたうえで、それを踏まえたより深い質問を準備しましょう。
また、面接ですでに話題にあがって説明を受けている内容を質問しないようにしましょう。すでに伝えられた内容を質問すると、相手の話を聞いていないと思われてしまい、印象が悪くなります。
③逆質問で持っていく質問を事前に複数用意する
逆質問では、事前に複数の質問を用意しておくようにしましょう。特にグループ面接では、他の応募者と質問が重複してしまう可能性があります。準備していた質問が使えなくなる場合に備えて、あらかじめ複数の質問を考えておくと安心です。
また、逆質問として用意していた質問の答えが、それまでの面接の会話の流れで出てしまうこともあります。すでに話題になった内容を再度質問するのはマナー違反なので、この場合も別の質問をする必要があります。
【コラム】面接で答えに詰まってしまったとき、あなたならどうする?

面接中に予想外の質問をされたり、緊張で頭が真っ白になったりして、答えに詰まってしまうこともあるでしょう。本番でこのような状況になっても対処できるよう、事前に対策を考えておきましょう。
面接で答えに詰まってしまったときは、以下の対処方法がおすすめです。
- 考える時間をもらう
- 完璧でなくてもできる限りベストな回答をする
- 分からないことは素直に分からないと伝える
すぐに回答ができないときは、「申し訳ございません、重要な質問なので少し整理させてください」などと伝えて時間をもらうことが大切です。無理に答えようとして誤った回答をすると信頼を損ねてしまう可能性があるため、一度落ち着いて考える時間をもらう方が良い印象を与えられます。
考える時間をもらったら、深呼吸をして心を落ち着かせ、質問の内容を再度確認しましょう。完璧な答えを求めすぎず、自分なりの考えを素直に伝えて、できる限りベストな回答をすることが重要です。
どうしても答えが思い浮かばない場合は素直に分からないと伝え、今後学んでいく意思を示すとよいでしょう。「大変申し訳ありません。まだ十分に知識が及んでおらず、的確なお答えができません。ただ、○○という点には関心があり、今後深く学んでいきたいと考えています」などと伝えると前向きな印象になります。
面接前後、電話やメールの連絡はどうするのが正解?

面接前には、面接の日程確認や予定変更、辞退などで連絡が必要になる場合があります。特に、面接の日程の変更を依頼したり、辞退する場合はメールで早めに連絡することが大切です。
面接後のお礼メールは必須ではないため送らなかったとしてもマイナス評価になることはありません。ただし、面接の当日または翌日にお礼メールを送ることで、熱意や志望度の高さが伝わるなど印象がよくなる場合があります。
面接にどうしても受からない…その原因と対策をチェックしてみよう

面接で思うような結果が出ない場合は、これまでの面接を客観的に振り返り、改善点を見つけることが重要です。
以下で面接に受からないときによくある原因とその対策方法を解説します。
①事前準備が足りていない
面接での失敗の多くは、事前準備をしっかり行うことで防ぐことができます。
事前準備とは、自己分析や企業研究を行い質問への回答を準備すること、模擬面接などで練習しておくこと、当日の持ち物や面接会場の確認などが考えられます。
たとえば、自己分析が足りていないと、他の応募者よりも印象に残る自己アピールができず採用に至らない場合があります。そもそも企業研究の不足から自分と相性のよくない企業に応募してしまっているケースも考えられます。
②服装や身だしなみに清潔感がない
第一印象は面接の成否を大きく左右するため、服装や身だしなみの清潔感は非常に重要です。服装がスーツというだけでは清潔感は得られないため、髪型、手の先、スーツの着こなし、持ち物の状態まで、あらゆる細部に注意を払うことが大切です。
スーツはサイズが合ったものを選び、シワや汚れがないか確認してください。男性の場合、髪は短く整え、ひげはきれいに剃り、爪は短く切りそろえるようにしましょう。女性の場合も、髪はすっきりとまとめ、メイクは派手すぎない自然な仕上がりを心がけることが重要です。
③自然体で望めていない・場慣れしていない
面接で緊張することは自然なことですが、緊張しすぎて本来の自分を表現できないと面接官に正しく評価してもらえません。過度な緊張を防ぎ、できるだけ自然体で面接本番に臨めるようにしましょう。
過度の緊張を防ぐには、事前の準備と練習をしっかりと行うことが効果的です。場馴れしていないことが原因と思われる場合は、大学のキャリアセンターで模擬面接を行い、本番形式の面接の流れに慣れておくことで本番での緊張を軽減できます。
また、前日以前に一度面接会場に行ってみて、面接会場や周辺の環境に慣れることも緊張緩和に役立ちます。
④一般常識が足りていない
一般常識やビジネスマナーが足りていないことで面接に受からないこともあります。特に、敬語の使い方、社会人としての基本的な知識が不足しているとマイナス評価となります。
敬語については、尊敬語、謙譲語、丁寧語の使い分けを正しく理解し、自然に使えるよう練習しておきましょう。
また、面接で一般常識としての時事問題が話題になることもあります。普段から新聞やニュースをチェックし、特に志望業界に関連する情報は敏感にキャッチしておきましょう。

まとめ

この記事では、就職活動で第一志望の内定を獲得するための面接対策について詳しく解説しました。
面接は、基本マナーから企業研究、質問への回答の事前準備、服装や持ち物の確認まで、大変なことが多い場面です。
1つ1つのポイントを入念にチェックし、抜け漏れがないことを確認することで、着実に成功率を上げていくことが重要です。