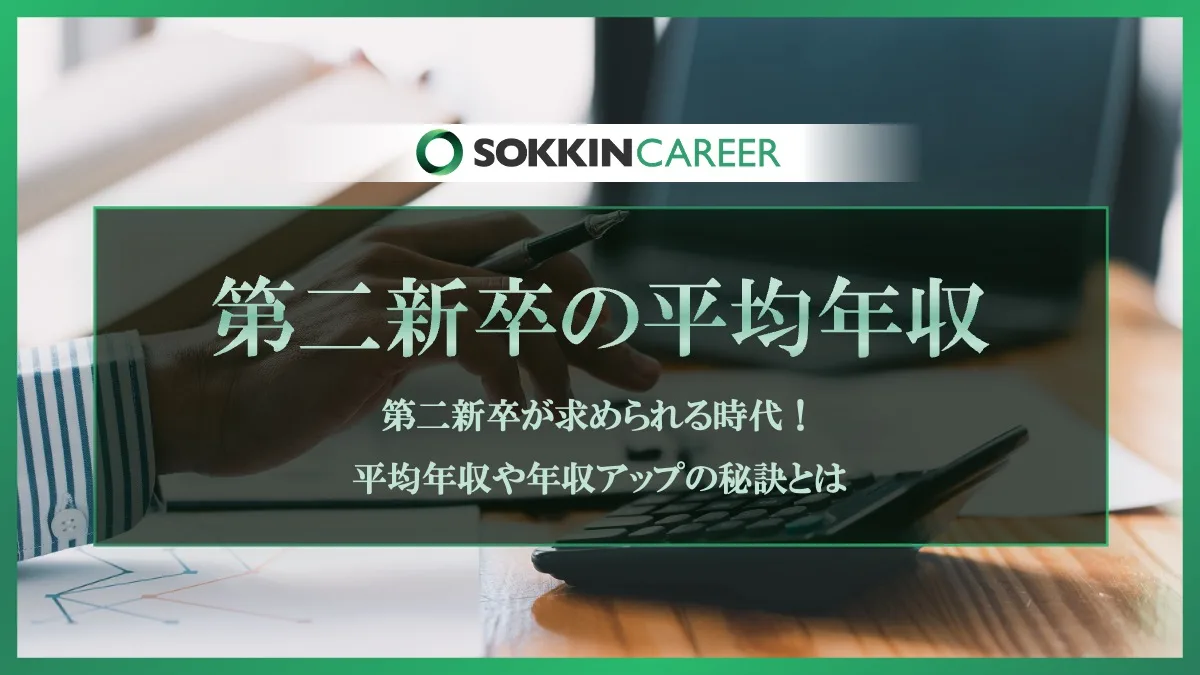第二新卒とは、新卒で入社した会社を数年以内に退職し、再び就職活動を始める社会人のことを指します。
以前はネガティブなイメージもありましたが、近年では多くの企業が積極的に第二新卒を採用する時代になっています。
しかし、「第二新卒の年収はどうなるの?」「新卒と比べてデメリットは?」など、疑問点や不安な点も出てくると思います。
この記事では、第二新卒の基礎知識や新卒、中途採用との違い、第二新卒のメリットや年収アップの秘訣などを解説します。
第二新卒に需要がある理由や、第二新卒で年収がアップするケースも詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

第二新卒とは

「第二新卒」とは、大学や高校などを卒業後に新卒で入社した会社を数年程度で退職して、再び就職活動を始めた人のことです。
一方で「新卒」は、学校を卒業してすぐに就職先に入社する新社会人のことを指しますので、第二新卒とは区別して扱われます。
何年目までが第二新卒なの?
第二新卒の定義には明確な基準はありません。一般的には「新卒入社後3年以内に退職した人」というのが目安ですが、具体的な年数が決まっているわけではありません。
たとえば、様々な転職サイトがありますが、「25歳未満」「入社5年目まで」などサイトによって第二新卒の定義は異なります。学歴によっても年齢は大きく変わりますので、あくまでひとつの目安と考えておきましょう。
また、新卒との年数の違いで見られますので、転職経験は基本的には関係ありません。ただし、採用の判断では転職回数が多いほど早期退職の懸念を持たれやすいため注意が必要です。
新卒、既卒、中途採用と第二新卒の比較

第二新卒によく似たものとして、以下のような言葉もあります。
- 新卒
- 既卒
- 中途採用
以下でそれぞれ第二新卒とどのように違うのか詳しく比較してみましょう。
第二新卒と新卒の違い
第二新卒と新卒の違いは、「社会人経験の有無」です。学校を卒業後にいずれかの企業で就職したことがある人が第二新卒と扱われます。
新卒は「新規卒業」を略した言葉です。学校を新規に卒業して、すぐに就職する人が新卒と呼ばれます。たとえば、2025年3月に大学を卒業して2025年4月に就職するのが新卒社員です。
一方で、一度どこかの会社で新卒社員として入社し、その後に退職を経験して別の企業に就職する人が第二新卒と呼ばれます。新卒で入社した際に一度社会人を経験しているという点が決定的な違いとなります。
第二新卒と既卒の違い
既卒とは、就職活動がうまくいかなかったなどの理由で学校を卒業後に一度も就職していない人のことを指します。
第二新卒は新卒で一度就職してから退職した人のことなので、就職経験があるかどうかが違いとなります。
既卒者は社会人経験がないため新卒と同等の教育が必要になり、就職活動では不利になる場合が多いです。
一方で、第二新卒は社会人経験があることから、スキルや社会人経験が評価されれば即戦力になれるという点に違いがあります。
第二新卒と中途採用の違い
中途採用は「新卒以外の社会人経験者すべて」を表す言葉です。第二新卒も広い意味での中途採用の中のひとつと言えます。
ただし、中途採用は専門性や即戦力を求めて採用されることが多いという特徴があります。即戦力になることが前提で、給与面でも最初から高額な年収が提示されることが多いです。
一方で、第二新卒は高度な専門性や豊富な経験を求められるのではなく、新卒に近いフレッシュな人材として扱われます。ある程度のビジネススキルを身に付けていることが前提になりますが、基本的にはこれから成長していく可能性を期待されるのが第二新卒です。


第二新卒のメリットとは

第二新卒は新卒と比べてネガティブなイメージを持つ人もいるかも知れませんが、第二新卒ならではのメリットもあります。
以下で第二新卒の強みとしてアピールできる2つのメリットを紹介します。
即戦力としてのポテンシャルがある
第二新卒のメリットは、社会人経験を積んでいるため、基本的なビジネスマナーや業務遂行能力があり、即戦力として期待できる点です。
たとえば、社内での報告・連絡などの基本的なコミュニケーションスキルや、基本的なビジネスマナーなど、社会人として必要な基礎知識を身に付けています。数ヶ月前まで学生だった新卒者と比較すると、入社後に時間をかけて教育する必要がないのは大きなメリットとなります。
第二新卒として転職活動をするときは、前職での業務経験やビジネススキルを身に付けていることをアピールすれば、初期の教育コストの削減が可能と判断されるため有利になるでしょう。
成長意欲が高い
新卒と比較して成長意欲が高い場合が多いのも第二新卒のメリットです。
転職の決意をした背景には、自身のキャリアアップへの強い意欲があることが多いです。前職で挫折があったとしても、そのことにより自分に合った環境で成長したいという意志が明確になっている人が多いでしょう。
このような、変化に柔軟に対応しながらスキルを磨く姿勢は、企業にとって大きな魅力となります。採用基準で人柄や意欲を重視する企業では、第二新卒の持つ成長意欲や前向きな姿勢が高く評価されます。
第二新卒に需要があるのはなんで?
近年では第二新卒の需要が高まっていて、企業が積極的に採用する時代になっています。
以下で、なぜ第二新卒に需要があるのか見ていきましょう。
第二新卒は育成にかかるコストが少ない
企業が第二新卒を採用する大きな理由となるのが、教育コストを抑えられるという点です。新卒と比較すると、基本的なビジネスマナーや社会人としての心構えが身についていることが多いため、初期の教育や研修を省略できるのがメリットです。
新卒の場合は入社後の数ヶ月間は研修期間と位置づけられることが多いです。最初にコストをかけて基本的なマナーや心構えを最初から教える必要があるのが特徴です。第二新卒ではここまで大掛かりな初期教育が不要となるため、即戦力として実践的な業務に早く取り組むことができます。
新卒の求人倍率が年々上がってきている
少子化の影響や大手企業に就職希望者が集中することが原因で、十分な人数の新卒を確保することが難しくなっている企業が増えています。このような企業では、新卒同様にフレッシュで柔軟性の高い第二新卒を積極的に採用する傾向があります。
ワークス大卒求人倍率調査(2024年卒)|リクルートワークスによると、従業員数300人未満の企業では、2024年3月卒の大卒の求人倍率は6.19倍という非常に高い数字となっています。企業規模を限定しない全体の倍率でも1.71倍となり、新卒の求人倍率は年々上がってきています。
新卒の求人倍率が上がれば上がるほど、第二新卒の需要も高まると考えられます。


第二新卒の給料ってどれくらい?

第二新卒として就職活動をするときに気になるのが、新卒や中途採用と比べた給料の違いではないでしょうか?
実は、新卒で入社した会社を退職して第二新卒になることで、年収が上がることもあれば下がることもあります。
以下で第二新卒の平均年収や、年収が上がるケースと下がるケースについて解説します。
第二新卒の平均年収
dodaの平均年収ランキングによると、第二新卒の平均年収は以下のようになっています。
| 年齢 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 | 男女合計 |
| 22歳 | 301万円 | 274万円 | 286万円 |
| 23歳 | 318万円 | 314万円 | 302万円 |
| 24歳 | 321万円 | 289万円 | 305万円 |
| 25歳 | 372万円 | 332万円 | 351万円 |
| 第二新卒全体 | ー | ー | 317万円 |
このように、第二新卒全体の平均年収は約317万円となっています。第二新卒も年齢が上がるほど年収も上がっていくことが分かります。
民間給与実態統計調査|国税庁の「年齢階層別の平均給与」では、20歳〜24歳全体の平均年収は269万円となっています。この数字を上記の表と比較してみると、第二新卒の年収は新卒も含めた全体の平均年収と大きな違いがないことが分かります。
参考として、同じ調査で35〜39歳の平均年収は449万円、40〜44歳は480万円、45〜49歳は504万円となります。勤続年数が長くなったり、中途採用で転職をすることで大幅な年収アップが実現できることが分かります。
また、全国就業実態 パネル調査 2024|リクルートワークスでは、「年収の増減状況(転職前と転職後1年目比較)」という調査があります。この調査によると、15歳〜24歳の年齢で転職を経験した人のうち、年収が10%以上増えた人は全体の36.4%、年収が10%以上減った人は20.5%という結果となっています。
新卒で入社後に早い段階で転職をした場合でも、結果的に年収アップにつながるケースは多くあることが分かります。
第二新卒の年収が上がるケース
すでにお伝えしたように、第二新卒の需要は年々高まっていて、独自のメリットもあります。
第二新卒として転職することで年収が上がるケースとして以下の3つのパターンがあります。
収入の高い企業へ転職した
最も多い年収アップのケースは、前職より収入の高い企業や業界に転職した場合です。
たとえば、不動産業や金融業、IT業界などは年収が高い業種の代表例です。また、インセンティブのある営業職や、システムエンジニア(SE)のような専門知識が求められる職種は年収が高くなります。
前職の業務経験や在職中に身に付けたスキルを活かして収入の高い企業や職種に転職できれば、新卒時の会社よりも年収アップを実現できます。
中途採用として採用された
企業によっては広い意味での「経験者採用枠」として第二新卒を採用することがあります。
前職での経験やスキルが転職先で高く評価された場合、中途採用として採用されることで新卒より高い給与がもらえることがあるでしょう。
このようなケースでは、中途採用を積極的に行っている企業を調査して、面接時に前職での具体的な業務成果や習得したスキルをアピールすることが重要です。即戦力として評価されれば年収アップにつながりやすくなります。
企業側との給与交渉に成功した
転職時に企業側との給与交渉に成功することで年収アップを実現できるケースもあります。すでにお伝えしたように人材不足で求人倍率が上がっていることから、企業側も優秀な人材を確保するために条件面で柔軟な対応をすることが多くなっています。
給与交渉を成功させるためには、自分の市場価値を客観的に把握して、実績やスキルを効果的にアピールすることが大切です。専任のコーディネーターが間に入って条件交渉をサポートしてくれる転職エージェントを活用するのもおすすめです。
第二新卒の年収が下がるケース
逆に、第二新卒として入社することで年収が下がってしまうケースもあります。
以下でよくある3つのパターンを紹介しますので参考にしてください。
新卒社員と同等の扱いになるから
第二新卒は社会人経験はあるものの、中途採用と比較すると経験が浅いため、転職先によっては新卒同様の扱いになることがあります。
特に、年功序列の考え方が強い企業では、勤続年収に応じた給与体系が適用されることが多いです。転職すると勤続年数はゼロから再スタートとなるため、前職より年収が下がることになります。
現状に満足出来なくて転職した
転職の理由は人それぞれですが、現状に満足できなくて転職した場合は、年収が下がるリスクがあります。
収入面や生活面などで前職の会社では満足できず退社したため、職がない状態で焦りが生まれてしまい、採用された会社にすぐ就職してしまうケースが多くなるからです。
たとえば、しっかりと事前準備をする余裕がなく、自分の市場価値を把握しないまま転職活動を進めてしまうケースがあります。
また、焦りから採用されやすさを優先してしまい、給与面で妥協すると年収ダウンにつながってしまいます。
未経験の分野に転職した
これまでと異なる業界や職種に未経験で転職する場合、スキルや経験が評価されにくいため、年収ダウンになることが多いです。新しい分野では新卒と同等の扱いとなるため、給与も初任給と同程度から始まることになります。


第二新卒が年収アップを狙うには

ここからは、第二新卒が継続的に年収アップさせるための具体的な方法やキャリアプランの考え方について見ていきましょう。
事前準備をしよう
年収アップを実現するためには事前準備が重要です。
まず、自分のスキルや経験を客観的に評価して、自身の市場価値を把握しておきましょう。そのうえで、自分に合った選択肢として副業や転職の可能性を検討してみるのがおすすめです。
また、自分の専門分野や興味のある分野での業界研究も重要です。年収の高い業界や企業について調査して、自分のスキルや興味との相性を考えてみましょう。
自身の継続的なスキルアップも含めた長期的な視点でキャリアプランを考えることが大切です。
副業を始めよう
第二新卒として入社した会社の業務に慣れてきたら、仕事終わりや土日の空き時間を使った副業を始めるのがおすすめです。
副業向けの人材マッチングサービスを利用すれば、本業の仕事と両立しやすい高収入の副業を探すことができます。
副業するならSOKKIN MATCH
副業をするなら人材マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです。
SOKKIN MATCHでは、主にマーケター、エンジニア、クリエイターの分野で業務委託の副業案件を探せる点が魅力です。
コーディネーターが案件探しをサポートしてくれるエージェント型のサービスで、精度の高いスキル診断を通じて自分に最適な案件を探すことができます。
面接対策や報酬交渉、スキルアップ支援など充実したサポートが受けられますので、本業を続けながら継続的な収入アップを目指せるでしょう。
転職も考えよう
もし今の現状に満足できていないなら、思い切って転職するのもひとつの選択肢です。
新卒と第二新卒で入社した2社での業務経験を活かして、中途採用枠で高収入の企業を狙っていきましょう。自身の能力やスキル次第では条件のよい転職先を見つけられる可能性は十分にあります。
転職活動をする際には、転職エージェントを利用することで自分に合った求人を効率的に探すことができます。面接対策や給与交渉のサポートも行ってくれるため、自分1人で転職活動を行うより年収アップを実現しやすくなるでしょう。
第二新卒の注意点

第二新卒にはメリットや強みもありますが、注意すべきポイントもあります。
以下で第二新卒として就職活動をするときに気をつけたい注意点を3つ解説します。
すぐに辞めてしまうのではないかと思われる
第二新卒の大きな注意点が、企業側が「すぐに辞めてしまうのではないか」と不安に思う可能性があることです。
新卒で入社した企業を一度早期退職しているため、「自社でも同じように早期退職してしまうのではないか」と懸念を持たれる可能性があります。
第二新卒を積極的に採用する企業が増えていますが、採用した人材はできるだけ長く勤めてもらいたいと考える企業がほとんどです。転職活動では、長期的に働きたいという意思を持っていることをアピールして、採用担当者の不安を軽減することが重要です。
即戦力であると期待される
第二新卒で採用されると、新卒よりも基本的なビジネススキルや業務理解がある前提で業務が進みます。即戦力であると期待されるため、新卒と比べると成長のためのサポートが少ないという注意点があります。
たとえば、一般的なビジネスマナーやコミュニケーションスキルは、あらためて研修をしなくても習得済みと判断されます。最初から実践的な業務を任される可能性が高いため、不足するスキルがあれば自ら行動して身に付ける必要があるでしょう。
採用面接でも、基本的な社会人スキルは持っていて、即戦力として活躍できると伝えることが大切です。教育コストが削減できるという第二新卒のメリットを強みとしてアピールできるようにしましょう。
転職した理由の明確化が必要
第二新卒は転職した理由の明確化が必要です。新卒で入社した職場を一度退職しているため、合理的な転職理由がないと採用担当者に不安を与えてしまうからです。
曖昧な転職理由を伝えると、「何か問題があって辞めたのではないか」「自社でもすぐに辞めてしまうのではないか」と懸念を持たれるため注意が必要です。
転職理由は新卒で就職活動をするときは問われないことなので、採用担当者にポジティブに伝えられるようしっかりと準備しましょう。
たとえば、「人間関係が悪かった」ではなく「より専門性を高められる環境を求めている」など、「なぜ前職を辞めたのか」「次の職場で何をしたいのか」を論理的に説明することが大切です。
まとめ
この記事では、第二新卒の特徴や新卒や中途採用との違い、メリットや年収などについて詳しく解説しました。
第二新卒は新卒で一度就職した後に、数年以内に退職して再び就職活動をする人のことを指します。中途採用と共通点もありますが、新卒のようにフレッシュな人材として将来の成長を期待されるという特徴があります。
第二新卒の給料は、採用されるときの状況によって年収がアップすることもあれば、年収が下がることもあります。まずは転職する理由を明確化し、第二新卒のメリットをポジティブな形でアピールすることが大切です。
第二新卒が年収アップを目指すには、これまでの社会人経験で得た能力やスキルを客観的に把握したうえで、副業や転職を検討してみるとよいでしょう。
ぜひこの記事でまとめたことを参考にしていただき、就職活動やキャリアプランニングで役立ててください。