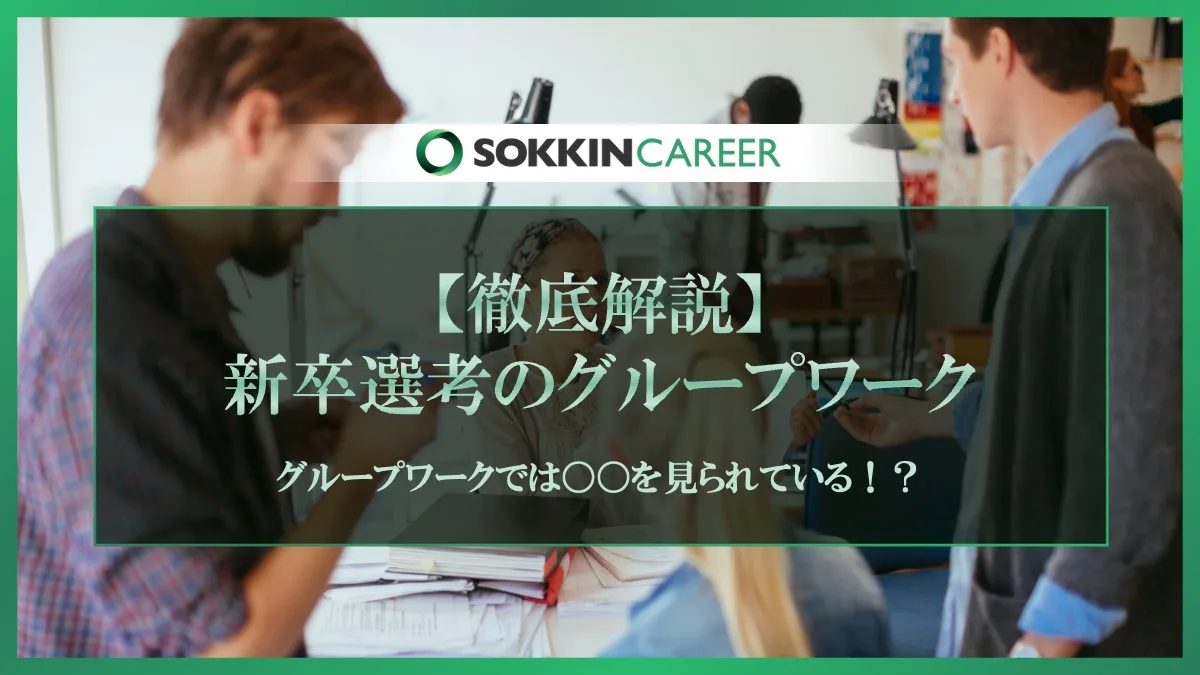就職を希望する業界・職種によっては、実施されることがあるのがグループワークです。グループワークは、インターンシップや本採用での導入が多く見られます。
グループワークを体験する新卒者のなかには、「目的・意図がどこにあるのかわからない」「苦手な人がうまくいくコツがあれば知りたい」といった疑問・悩みを抱えている人が少なくありません。
本記事では、新卒者向けにグループワークの全容を解説します。実施される目的・対策・注意点なども含めて網羅的に紹介するので、ぜひ参考にしてください。
グループワークとは?

そもそもグループワークとは、どういうものなのでしょう。グループワークについて解説するので、理解を深める際の参考にしてください。
グループワークの目的について
グループワークの目的は、本選考とインターンシップで異なります。
本選考では、マッチング度の見極めが目的です。主に以下のような点に注目して、評価しています。
- 協調性
- 論理的思考力
- コミュニケーション能力
一方のインターンシップでは、以下のような点を目的として実施されることが一般的です。
- 企業理解
- 仕事の面白さを体感
- 入社意欲の向上
企業側は優秀な学生の早期発見やブランディングを目的とし、学生側は自身の成長や企業選びの参考にします。

グループディスカッションとの違い
グループワークとグループディスカッションは密接な関係にありますが、成果物の有無が主な違いです。
グループディスカッションは、与えられたテーマについて議論して結論を導き出すプロセスを評価の中心に設定しています。
一方、グループワークはグループディスカッションを含む議論を経て、「具体的な成果物」を作成して発表するまでの一連の共同作業が評価対象です。
グループワークの進め方
グループワークの進め方について紹介しましょう。
自己紹介
グループワークにおける自己紹介は、円滑な議論のスタートを切るために重要です。
単に名前を名乗るだけでなく、氏名、大学名、意気込みなどを簡潔に伝えましょう。特に、今回のグループワークで貢献したいことや自分が得意な分野を共有すると、後の役割分担や議論がスムーズに進みます。
役割分担と時間配分
グループワークを成功させるには、役割分担と時間配分が鍵を握っています。特定の役割に評価差はなく、全員がチーム貢献を目指す意識が重要です。
まず書記・タイムキーパー・アイデア出し・発表者などを決め、各自が責任を持って議論に臨むことで効率が上がります。
次に与えられた時間を議論・情報整理・成果物作成・発表練習に割り当て、進捗を随時確認しましょう。これにより、時間内に質の高い成果物の作成とスムーズな進行が実現可能です。
言葉の定義や議論の方向の共有
グループワークをスムーズに進めるには、まず言葉の定義や前提条件を共有することが極めて重要です。
議論を始める前に、共通認識を確立しましょう。さらに議論の方向性や目的を全員で共有することで、無駄な回り道を避けて効率的かつ質の高い成果につながります。
これにより認識のズレを防ぎ、建設的な議論が展開できるでしょう。
課題・論点・ゴール設定
グループワーク開始時、まず与えられた課題を正確に理解することが重要です。表面的な情報だけでなく、「なぜこの課題が出されたのか」「何が問われているのか」という論点を深掘りしましょう。
次にグループとして最終的に何を達成するのか、具体的なゴールを明確に設定します。誰もが納得できる具体的な成果イメージを共有することが重要です。
議論の方向性が定まり、効率的に質の高いアウトプットが生み出せるでしょう。

討論開始
ゴール設定ができたら、次はいよいよ議論を本格的に開始します。ここでは、まずアイデアを広げる「発散」と、それを整理してまとめる「収束」の2つのステップを意識すると、議論がスムーズに進みます。
アイデアを発散させる
まずは質より量を重視し、自由な発想でアイデアをたくさん出すことに集中しましょう。この段階では、他の人の意見を否定したり、実現可能性を考えすぎたりしないことが重要です。
「こんなことを言ったら笑われるかも」と臆せず、誰もが自由に発言できる雰囲気作りが欠かせません。もし発言が少ないメンバーがいれば、「〇〇さんはどう思いますか?」と話を振るなど、全員が議論に参加できるよう配慮しましょう。
アイデアを整理・収束させる
十分にアイデアが出たら、次はそれらを整理していきます。
似たような意見をグループにまとめたり、それぞれのアイデアのメリット・デメリットを比較検討したりして、論点を絞り込んでいきましょう。ホワイトボードや付箋(ポストイット)を使い、全員の意見を可視化しながら進めると、認識のズレを防ぎ、効率的に議論を整理できます。
結論の検討
グループワークの最終段階では、これまでの議論や分析に基づいて最適な結論を導き出すことが重要です。
複数の選択肢がある場合は、それぞれのメリット・デメリットを比較検討して根拠を明確にして最も説得力のある結論を選びましょう。メンバー全員が納得できるか、与えられた課題解決につながっているかに注目して議論してください。必要であれば修正を加えることで、質の高いアウトプットが完成します。
結論の最終決定
グループワークの結論の最終決定は、チームの集大成です。
これまでの議論と分析を基に、最も説得力のある解決策や提案を具体的にまとめます。重要な点は、その結論に至った理由を明確な根拠とともに示すことです。
メンバー全員が納得し、自信を持って発表できるよう、意見のすり合わせを徹底してください。必要であれば、表現を調整しましょう。論理的かつ簡潔に、メッセージが伝わるように仕上げることが成功の鍵を握っています。

グループワークの評価ポイント

グループワークの評価ポイントについて、確認していきましょう。
コミュニケーション能力
グループワークにおけるコミュニケーション能力は、質が重視されます。具体的には、以下のようなポイントがあげられるでしょう。
- 自身の意見を論理的かつ明確に伝えられるか
- 相手の意見を傾聴して理解に努めているか
- 異なる意見への尊重
- 建設的な議論を促せるか
- チーム全体の合意形成への貢献度
論理的思考力
論理的思考力も、グループワークにおける評価ポイントです。課題を正確に分析し、筋道を立てて解決策を導き出す能力が評価されます。
具体的には、評価ポイントは以下の通りです。
- 現状分析
- 課題の特定、根本原因の深掘り
- 自身の意見や提案に明確な根拠やデータを示せるか
- 複数の情報を整理して一貫性のある論理を構築できるか
非論理的な意見に流されることなく冷静に問題の本質を見極め、建設的な議論をリードできるかが評価の鍵となります。
主体性
主体性も、グループワークにおける評価ポイントのひとつです。グループワークで重視される主体性は、単に積極的に発言するだけではありません。自ら課題を見つけ、解決に向けて行動する姿勢が評価されます。
具体的な評価ポイントとして、以下のような点があげられるでしょう。
- 自ら率先して意見を提案
- 必要な情報の収集
- 議論が停滞した際に改善策を提示
- チーム全体を巻き込む推進力
協調性
協調性は、グループワークで重視される評価ポイントです。グループワークにおける協調性は、単に周りに合わせることではありません。チーム全体の目標達成に向けて、他者と協力し、貢献しようとする姿勢が評価されます。
具体的な評価ポイントとして、以下のようなものがあげられるでしょう。
- 異なる意見の尊重
- 建設的な対話
- 合意形成
- 自身の役割を明確に認識する能力
- 他のメンバーをサポートできる
- チーム内の雰囲気を良好に保てるか
- ポジティブな影響を与えられるか
自分の意見を主張するだけでは、満足な評価は得られません。チーム全体のパフォーマンスを最大化するために、柔軟に対応できるかがポイントといえます。
素直さや思考の柔軟性
グループワークにおける素直さや思考の柔軟性は、新たな視点を取り入れてより良い結論を導くうえで重要です。
具体的には、以下のような点があげられます。
- 自身の意見に固執しない
- 他者の意見やフィードバックを真摯に受け入れられる
- 迅速かつ建設的な軌道修正できる
予期せぬ状況や情報の変化にも柔軟に対応し、多様な意見を統合して最適な解決策を模索できるかが評価の鍵となります。
集中力
グループワークにおける集中力は、限られた時間で成果を出すために不可欠です。
具体的には、以下のようなポイントが評価されます。
- 常に課題解決に向けて意識を向けられるか
- 他のメンバーの発言を注意深く聞く傾聴力
- その内容を正確に理解できるか
- 自身の意見を効果的に構築できるか
議論が停滞したり意見が対立したりする状況でも、冷静さを保って最後まで粘り強く思考を継続できるかが評価のポイントとしてあげられます。

グループワークの種類
グループワークの種類を紹介するので、参考にしてください。
作業型グループワークのテーマ例
作業型グループワークのテーマ例について解説します。
実物作成型
実物作成型グループワークは、議論に加え、企画書や模型などの具体的な成果物をチームで制作する形式です。
このグループワークは、単なる議論に終わりません。アイデアを形にする実践力や協調性、創造性が評価されます。
プラン形成型
プラン形成型グループワークは、与えられた課題に対してチームで戦略や具体的な企画を立案する形式です。
市場分析やターゲット設定を行い、実現可能性の高いビジネスプランや解決策を構築する論理的思考力と協調性が評価されます。
プレゼン型グループワークのテーマ例
プレゼン型グループワークのテーマ例について確認していきましょう。
自由討論型
自由討論型グループワークは、与えられたテーマについてチームで自由に議論を深める形式です。
チームとしての意見をまとめ、発表することがゴールとなります。
議論のプロセスにおける論理的思考力、傾聴力、合意形成能力が評価されます。
ビジネス型
ビジネス型グループワークは、企業が直面する実際の課題をテーマとして、解決策や新規事業を立案する形式です。
市場分析・戦略策定・プレゼンテーションを通じて、ビジネスへの理解度・論理的思考力・実行力が評価されます。
課題解決型
課題解決型グループワークは、与えられた具体的な問題に対してその原因分析から最適な解決策を導き出す形式です。
論理的思考力・課題特定能力・チームでの合意形成力が評価されます。
選択型
選択型グループワークは複数の選択肢の中から最も適切なものを選んで、その根拠をチームで議論し発表する形式です。
意思決定プロセスにおける論理的思考力・情報分析力・合意形成能力が評価されます。
フェルミ推定型
フェルミ推定とは情報が少ないなかで論理的な思考と概算を重ね、答えの近似値を導き出す手法です。
フェルミ推定型グループワークでは、与えられた漠然とした問いに対して論理的な仮説と概算で近似値を導き出します。
ゲーム型グループワークのテーマ例
ゲーム型グループワークは、ボードゲームやカードゲーム形式で課題解決に取り組むものです。
資源配分ゲームや無人島脱出ゲームなどで、楽しみながら論理的思考力や協調性を評価します。

グループワークでの4つの役割

グループワークでの4つの役割について確認していきましょう。
ファシリテーター
グループワークにおけるファシリテーターは、議論を円滑に進める進行役です。
ファシリテーターは、特定の意見を主張する立場にはありません。中立的な立場で全員の発言を促し、意見を整理して方向性がブレないように調整します。タイムキープや認識のズレ解消といった重要な役割を担う欠かせない存在です。
チーム全体の力を最大限に引き出し、質の高い結論へと導くことが求められます。
タイムキーパー
グループワークにおけるタイムキーパーは、与えられた時間を管理して議論の進捗を促す重要な役割です。
タイムキーパーが担っている役目は、単に残り時間を伝えるだけではありません。議論が脱線していないか確認したり、次の議題への移行を促したりすることも、役割のひとつです。時間内に有意義な結果を出すために、積極的に関与することが求められるでしょう。
書記
グループワークにおける書記は、議論の内容を正確に記録する重要な役割です。
その役割は、単なる議事録作成に留まりません。出された意見や決定事項、課題などをリアルタイムで整理してメンバー全体に共有することも重要な役目です。このような役目を担うことで、議論の見える化が促進されるでしょう。
論点の整理や認識の齟齬を防ぎ、効率的な議論と質の高い結論の導き出しに貢献します。
役職なし
グループワークにおいて特定の役職がない場合でも、チームへの貢献は十分に可能です。
議論の活性化のために積極的に発言したり、意見がまとまらない際に現状を整理して発言を促すなど、場を支える役割を担います。タイムキーパーを意識して発言時間を調整することや、メンバーの意見を引き出す質問をすることも有効です。
役職はありませんが、柔軟な立ち回りが求められる立場にあるといえるでしょう。
グループワークが上手くいくコツ
グループワークが上手くいくコツについて紹介するので、参考にしてください。
自分の得意な役割を把握する
グループワークを成功させるには、自分の得意な役割を把握することが非常に重要です。
例えばアイデア出しが得意なら積極的に新しい視点を提供し、議論を活性化させましょう。書記が得意なら、論点整理や情報共有でチームを支えられます。
またタイムキーパーやファシリテーターのように、議論の進行をサポートする役割も大切です。
チームで結果を出すことを意識
グループワークでは、個人の能力を示すだけでなく、チームとして最高の成果を出すという意識が非常に重要です。たとえ自分の意見が採用されなくてもチームの決定を尊重し、その実現に向けて最大限貢献しましょう。
議論が白熱しすぎたり意見が対立したりしても、最終目標はチームでの成功です。個人的なこだわりよりも、全体のゴール達成を優先してください。協力姿勢を示すことで質の高いアウトプットが生まれ、結果的にあなた自身の評価にもつながります。
タイムキーパー以外も時間配分を意識する
グループワークではタイムキーパーだけでなく、メンバー全員が時間配分を意識することが成功の鍵です。議論が盛り上がりすぎたり論点に固執したりすると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
各自が「今何に時間を使っているか」「残り時間で何をすべきか」を常に意識し、効率的な進行を心がけましょう。

グループワークが苦手な人へのコツ
誰もがグループワークが得意なわけではありません。なかにはグループワークに苦手意識を持っている人もいるでしょう。
グループワークが苦手な人に向けたコツを紹介するので、克服する際の参考にしてください。
わからないことは素直に聞く
グループワークが苦手な人にとって、わからないことを素直に聞くことは非常に重要です。理解できていない点を放置すると、議論から置いていかれてチームに貢献できません。
わからない点を具体的にあげて、遠慮せずに質問しましょう。素直に聞くことは、自身の理解力を深めるだけではありません。チーム全体の認識のズレを防ぎ、より質の高い議論につながります。
質問は、積極的な姿勢を示すことにも役立ってくれるでしょう。
初めにお互いを知る時間を作る
グループワークが苦手な方は、議論に入る前に簡単な自己紹介タイムを設けるのがおすすめです。
出身・趣味・今日の意気込みなどを軽く話すことで、心理的な壁が下がります。リラックスできるので、意見も出しやすくなるでしょう。
他のメンバーの発言に反応を示す
グループワークが苦手でも、他のメンバーの発言に積極的に反応を示すことで、議論への参加意識を高められます。相槌や軽くうなずくことで、発言者は安心して意見を出しやすくなるからです。
共感や理解を示すことでチームの一員としての存在感を示し、円滑なコミュニケーションを促進しましょう。

グループワークの注意点

グループワークでの注意点について紹介します。
スムーズにグループワークを進めるとともに高い評価を得るためにも必要なことなので、ぜひ参考にしてください。
結論ファーストにする
グループワークでは、結論ファーストで話すことを意識しましょう。
特に発表時や議論の要約時には、まず最も伝えたい結論や提案を明確に提示することが重要です。その後に理由や根拠を具体的に説明することで、聞き手に内容がスムーズに伝わります。
これは限られた時間で効率的に情報を共有し、聞き手の理解を深める上で非常に有効です。冗長な前置きや説明から入ると聞き手は話の全体像を掴みにくくなり、混乱を招く可能性があります。常に「何が言いたいのか」を明確にして発言しましょう。
全員に発言をしてもらう
グループワークでは一部のメンバーだけが発言し、他の人が黙ってしまうことがあります。これでは多様な視点が得られず、議論が深まりません。
ファシリテーターが中心となって、発言機会が少ないメンバーにも積極的に意見を求めるよう意識しましょう。全員が安心して発言できる雰囲気を作り、それぞれの知見を引き出すことで、チーム全体の成果および評価につながります。
すぐにできるグループワーク事前対策
今からでもすぐにできるグループワークの事前対策を紹介するので、参考にしてください。
最新のトレンドや業界知識を身につける
グループワークでは、最新のトレンドや業界知識が議論の説得力を高めることが重要です。
日頃からニュースや専門誌に目を通し、関連企業の動向や市場の変化を把握してください。これにより、具体的な事例を挙げながら発言でき、論理の深みが増します。
知識があることで自信を持って議論に参加でき、チームへの貢献度も高まるでしょう。
ロジカルシンキングを鍛える
グループワークでは、ロジカルシンキングが非常に重要です。
日頃から、ニュース記事や身の回りの問題に対し、「なぜそうなるのか?」「他にどんな選択肢があるか?」と常に問いかけ、原因と結果を論理的につなげる練習をしましょう。
漏れなくダブりなくが徹底できるMECEや、フレームワークの活用を意識してください。議論で説得力のある発言ができ、課題解決能力が向上します。
意見を言う能力・聞く能力を鍛える
グループワークでは自分の意見を明確に伝える力と、相手の意見を正確に理解する力が不可欠です。
日頃から、友人との会話で「自分の考えを論理的に話す練習」や、「相手の話の要点を掴む練習」を意識してください。テレビの討論番組を見ることも、効果的な練習方法です。聞く際は相槌を打ち、要約して確認しましょう。理解度と積極性を示します。
日頃から自分の考えを形にする
グループワークでは、漠然としたアイデアを具体的な形にする力を発揮しなければなりません。
何か課題に直面した際には、「どうすれば解決できるか」「どんな企画が考えられるか」といった問いを立てる癖をつけましょう。箇条書きや簡単な図で整理する方法をおすすめします。
これによりグループワークに臨んだ際には、論理的かつ説得力のあるアウトプットをスムーズに生み出せるようになるでしょう。
就活イベントに参加する
グループワーク対策として、就活イベントへの参加は非常に有効です。
企業が開催する説明会や合同説明会には、グループワーク体験ができるプログラムが含まれることがあります。実際に多様な学生と交流して模擬グループワークに参加することで、実践的な経験を積めるのでおすすめです。

まとめ
新卒者向けのグループワークについて解説しました。
グループワークは面接・書類選考ではわかりづらい候補生の特徴・特性などを確認するうえで、有効性の高い方法です。しかしグループワークに参加する側にとっては機会が少ないため、戸惑う人も少なくありません。
本記事では、グループワークの進め方・評価ポイントなども含めてさまざまな角度から解説しました。コツ・事前対策も紹介したので、これらを参考にしてグループワークの対策を講じてください。