
ES(エントリーシート)の書き方に悩む就活生は少なくありません。
なんとなく項目を埋めるだけでは、採用担当者の心に響くESは書けないからです。
ESで大切なのは、何を書くかではなく「何が評価されるのか」を理解すること。
本記事では、ESの基本的な書き方から企業が見ている基準、採用されるポイントまでをわかりやすく解説。特に重要な項目に関しては、例文も交えて丁寧に紹介します。
まだESに手をつけていない方も、すでに書き始めている方も、ぜひ本記事を参考にしてください。

ESとは?
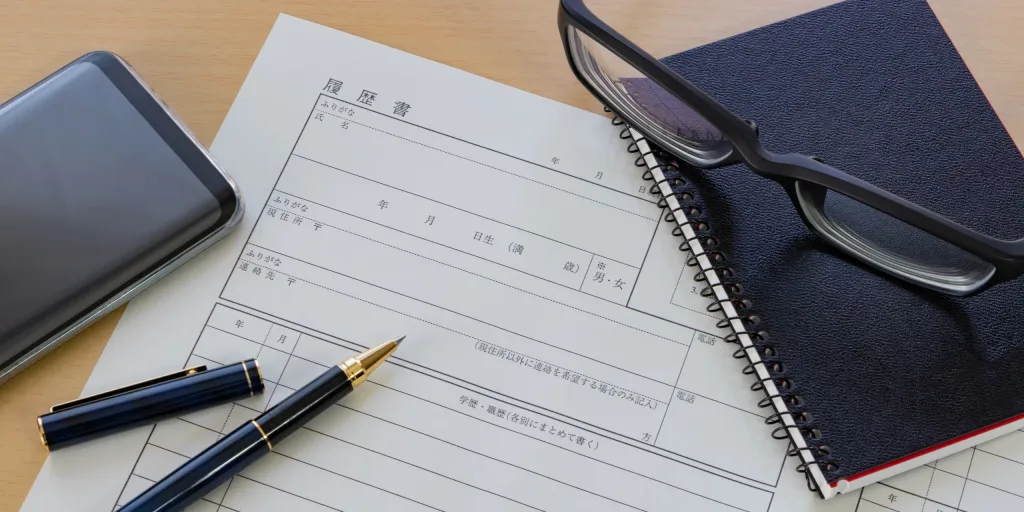
ESとは、「エントリーシート(Entry Sheet)」の略で、就職活動の際に企業へ提出する書類のことです。
主に、志望動機や自己PR、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)などが設問として出され、応募者の人柄や価値観、考え方を知るために活用されます。
企業は、ESの内容をもとに、自社にふさわしい人材かどうかを見極めます。

履歴書との違いは?
履歴書とESには、書類の使われ方に大きな違いがあります。
履歴書は、応募者の個人情報などを確認・保管する書類である一方、ESは、主に選考・面接のために使われる書類です。
履歴書が「基本的な情報(名前や住所、学歴など)」を伝えるのに対し、ESは「採用に必要な情報(人柄や考え方、個性など)」を伝えます。
- 履歴書:市販(コンビニや大学の生協など)の用紙を使って提出するのが一般的
- ES:企業ごとのフォーマットに沿って、オンライン上で提出するのが基本
伝える内容を混同しないためにも、両者の違いを理解しておきましょう。

ESを書き始める前に注意する基本のポイント
ESは多くの場合、オンライン上のフォームに入力して提出しますが、企業によっては紙に記入するケースも存在します。そのため、ESを書き始める前に、基本のポイントを理解しておくことが大切です。
どちらもESに限らず、ビジネス文書としての基本です。誤字脱字や文章表現のミスを防ぐためにも、あらかじめルールを押さえたうえで丁寧に仕上げましょう。
使用する筆記用具に注意する
紙のESを書く場合は、「黒のボールペン」または「万年筆」を使用しましょう。
文字は丁寧に、読みやすさを意識して書くことが大切です。書き始める前には一度下書きをして、誤字脱字や内容を確認してから清書すると、安心して提出できます。
文章表現に注意する
ESでは、言葉遣いや文体にも注意が必要です。
- 第一人称:「私」
- 文体:「です・ます調」、または「である・だ調」に統一
また、略語(例:就活→就職活動)や話し言葉、絵文字など、カジュアルな表現は避けてください。ESを書き終えたあとは必ず読み返し、誤字脱字やミスのない整った文章に仕上げることが大切です。

企業がESで見ている基準

企業はESを通じて、応募者が自社にふさわしい人材かどうかを見極めています。
1. 応募者が会社の求める人材かどうか
2. 応募者の熱意や本気度
3. 応募者の文章作成・情報伝達能力
ESで書類選考を突破するには、企業がどんな視点で評価しているのかを理解し、それらを踏まえた内容を書くことが重要です。
ここでは、企業がチェックしている3つの観点について、詳しく解説していきます。

応募者が会社の求める人材かどうか
どれほど優れた経験やスキルがあっても、企業のニーズに合っていなければ、書類選考は通過できません。
大切なのは、企業がどのような人物を求めているのかを知ること。そのうえで、自分の強みや価値観が、企業の方向性とどのように重なるのかを考えましょう。
自分の強みが企業の求める人物像と全く異なる場合、当然ですが評価されにくいです。
応募者の熱意や本気度
ESには、多くの応募者が同時にエントリーしており、企業側に熱意を伝えるのは容易ではありません。そのなかで目を引くには、一貫した情熱を文章で示す必要があります。
ポイントは、志望動機や自己PR、ガクチカなどの項目に、軸の通ったストーリーや姿勢が感じられるかどうかです。一部の項目のみに力を入れても、形だけの熱意と受け取られてしまう恐れがあります。
応募者の文章作成・情報伝達能力
企業は、ESを通して、入社後に必要な文章作成・情報伝達能力のレベルを見ています。
そのため、内容の良し悪しだけではなく、相手に配慮した伝え方ができているかも重要です。
文章作成では、誤字脱字や文章表現のミスに気をつけることはもちろん、言葉選びや文の構成にも注意を払ってください。また、自分の考えや想いを、どうすればより伝わる内容にできるかを意識することも大切です。

ESの書き方/例文・コツについて

ESを書く際は、「企業がESで見ている基準」で解説した3つのポイントを意識することが重要だとお伝えしました。加えて、これから解説する基本的な書き方やコツ、例文を理解すれば、より伝わるESが完成します。
・基本情報
・学歴・職歴
・志望動機
・自己PR
・ガクチカ
・長所・短所
基本情報の書き方
基本情報を書く際に注意したいのが「正確性」です。
日付は提出日を記入し、「西暦」か「元号」かを応募書類全体で統一しましょう。
証明写真は、明るい表情で顔がはっきりと写っているものを選び、基本的にはスーツを着用します。また、裏面には学校名・学部・氏名の記入を忘れないようにしてください。
- 住所:省略せずに番地や部屋番号まで丁寧に記載
- 連絡先:固定電話がない場合は、携帯電話で問題なし
- メールアドレス:読み間違いの起きやすい英数字(oや0など)に注意
押印が必要な場合は、朱肉を使ってきれいに押しましょう。
学歴・職歴の書き方
学歴・職歴は、記入ルールを守ることが大切です。
・「中学校以下」は記入不要
・高校ではなく「高等学校」と記入
・大学名には「学部・学科」まで明記
・「卒業見込年度」を記入
■職歴のポイント
・「アルバイト・インターン(長期含む)」は記入不要
・「正社員としての職歴がある場合」のみ記入
基本的に、学歴も職歴も略語や省略表現は避け、具体的な名称を書くように心がけてください。ただし、一部省略可能な要素もあるため、各ポイントを参考にルールを守って書きましょう。

志望動機の書き方
志望動機は、企業との接点を明確にすることが重要です。
書き方は、「結論→理由→具体例→まとめ」のPREP法や、「要点→詳細→要点」のSDS法などのフレームワークを活用すると、論理的に伝わりやすくなります。
最後に、自身の強みと企業が求める人物像にズレがないかを確認して、一貫性のあるメッセージに仕上げてください。
志望動機の例文:企業理念に惹かれた場合
現代社会において、デジタル技術の活用格差は企業の成長を大きく左右します。特に中小企業や地方企業では、マーケティングの専門知識や最新技術へのアクセスが限られているという現実があります。貴社が掲げる「デジタルデバイドの解消」は、単なるビジネス目標ではなく、社会全体の発展に寄与する崇高な使命だと感じています。
私は大学でデータサイエンスを専攻し、統計解析やAI技術の基礎を学んできました。また、学生団体での活動を通じて、地方の中小企業がデジタルマーケティングに苦戦している現状を目の当たりにしました。この経験から、技術的な知識と地域企業への理解を活かし、貴社の「ALWAYS SOKKIN」のようなソリューション開発に携わりたいと強く願っています。
特に、AIや統計解析を組み込んだマーケティングツールの開発プロジェクトに参加し、中小企業でも手が届く価格帯でありながら高い効果を生み出すシステムの構築に貢献したいと考えています。私の分析力と課題解決への情熱が、貴社の理念実現に役立てると確信しています。
志望動機の例文:実際に行なっている事業に惹かれた場合
貴社の事業は、広告代理・運用支援、人材マッチング、自社メディア運営、オンライン講座という四つの柱が相互に連携し、マーケティング業界全体のエコシステムを構築している点が非常に革新的です。単なるサービス提供ではなく、人材育成から実際の運用まで一貫してサポートする仕組みは、業界の発展に大きく貢献していると考えます。
私は大学でマーケティング理論を学び、インターンシップでは人材紹介会社でマッチング業務を経験しました。この経験を通じて、優秀な人材と適切な企業を結びつけることの価値と難しさを実感しました。また、学生時代には複数のWebメディアを運営し、コンテンツ制作からSEO対策まで幅広く経験を積んできました。
特に、来期開始予定の新卒紹介事業の立ち上げフェーズに参加し、マーケティング業界の次世代人材と企業をつなぐ新しい仕組みづくりに貢献したいと考えています。私のマッチング経験とコンテンツ制作スキルを活かし、貴社の人材と企業を繋ぐエコシステムの拡大に尽力したいと思います。

自己PRの書き方
自己PRは、自身の強みを企業にアピールする重要な項目です。
内容が曖昧だったり、抽象的だったりすると、魅力が伝わらないため注意が必要です。
最後に、こうした強みが入社後にどう活かせるのかを記載しておくと、より伝わる文章になるのでおすすめです。
自己PRの例文
大学2年次に所属していたボランティアサークルで、地域の高齢者向けイベントの企画・運営を担当した際、メンバー間で意見の対立が生じ、準備が停滞してしまいました。私は各メンバーの意見を個別に聞き取り、それぞれの想いや懸念点を整理した上で、全員が納得できる折衷案を提示しました。具体的には、イベント内容を午前は文化的な催し、午後はレクリエーションに分けることで、異なる志向を持つメンバーの意見を両立させました。
さらに、準備期間中は率先してメンバー間の情報共有を密にし、進捗状況を可視化するツールを導入することで、チーム全体のモチベーション維持に努めました。その結果、当初予定していた参加者数を30%上回る120名の地域住民の方々にご参加いただき、アンケートでも95%の満足度を得ることができました。
この経験を通じて、多様な価値観を持つメンバーをまとめ、共通の目標に向かって推進する力を身につけました。貴社においても、この協調性とリーダーシップを発揮し、チーム一丸となって成果を上げることに貢献したいと考えています。

学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)
学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)では、「何を頑張ったのか」だけではなく、「どう成長したか」が問われます。
まずは、学生時代に力を入れたことを端的に示しましょう。そのうえで、努力や工夫を具体的に書いていきます。
企業が知りたいのは、あなたがどう困難を乗り越え、何を学んだのかという点です。
一過性の出来事ではなく、成長過程を論理的に伝える構成を意識しましょう。
ガクチカの例文:アルバイト
入社当初、私が担当した中学3年生5名のうち4名が平均点を下回る状況でした。従来の指導方法では生徒たちの集中力が続かず、宿題の提出率も30%程度と低迷していました。この状況を改善するため、まず生徒一人ひとりとの面談を実施し、勉強に対する不安や将来への悩みを聞き取りました。その結果、多くの生徒が「勉強の方法が分からない」「頑張っても成果が見えない」という共通の課題を抱えていることが判明しました。
そこで私は、各生徒の理解度に合わせた個別カリキュラムを作成し、小さな目標設定と達成感を重視した指導方法に変更しました。具体的には、週単位の小テストを導入し、合格点を取るごとにポイントを付与する仕組みを構築しました。また、保護者との連携を強化し、家庭学習の進捗を共有する体制を整えました。
この取り組みの結果、半年後には担当生徒全員の宿題提出率が90%を超え、定期テストの平均点も20点以上向上しました。最も成績が低かった生徒は志望校に合格を果たしました。この経験を通じて、相手の立場に立って課題を分析し、個別最適化されたアプローチを設計する力を身につけました。
ガクチカの例文:サークル・部活
3年生の時に幹事長に就任した際、サークルは深刻な状況にありました。部員数は前年の80名から45名まで減少し、年4回開催する定期ライブの観客動員数も平均150名から80名まで落ち込んでいました。部員へのヒアリングを行った結果、「練習環境の悪化」「先輩後輩の交流不足」「外部への発信力不足」という3つの主要課題が浮き彫りになりました。
これらの課題解決のため、まず大学との交渉を重ね、使用できる練習室を週3回から毎日利用可能に拡大しました。次に、学年を越えたバンド編成を促進するセッション企画を月2回開催し、部員間の結束を強化しました。さらに、SNSを活用した積極的な情報発信と、他大学サークルとの合同イベント企画に取り組みました。
特に力を入れたのは、地域の商店街と連携したストリートライブイベントの企画です。商店街の活性化と学生の発表機会創出を両立させるこの取り組みは、地元メディアにも取り上げられました。
これらの施策により、翌年には部員数が70名まで回復し、定期ライブの観客動員数も200名を超えるまでに成長しました。この経験を通じて、組織の課題を多角的に分析し、ステークホルダーを巻き込んだ解決策を実行する力を身につけました。
ガクチカの例文:学業
3年次に参加したゼミでは、人口減少に悩む地方自治体の課題解決策を検討するプロジェクトが始動しました。私たちのチームは岩手県の過疎地域をフィールドとして選択しましたが、当初は統計データの読み方すら十分に理解できていない状況でした。また、チームメンバー6名の研究レベルにばらつきがあり、議論が噛み合わないという課題もありました。
この状況を打開するため、私は毎週の勉強会を提案し、統計解析ソフトの使い方から政策立案の基礎理論まで、メンバー全員で学習する体制を構築しました。さらに、現地調査の重要性を説き、夏休みを利用して3泊4日の現地フィールドワークを企画・実行しました。現地では住民30名へのインタビュー調査を実施し、行政資料だけでは見えない地域の実情を把握しました。
収集したデータを基に、「若者定住促進のための起業支援策」という政策提言をまとめ上げました。特に、空き家活用と移住者のスキルマッチングを組み合わせた独自のアイデアを盛り込みました。
この研究成果を全国学生政策提言コンテストに応募した結果、200チーム中10位入賞を果たしました。この経験を通じて、複雑な社会課題に対してデータに基づいた論理的思考で解決策を導く力と、チームをまとめて目標達成に導くリーダーシップを身につけました。
ガクチカの例文:日常生活
大学入学と同時に実家を離れ、仕送りが月8万円という限られた予算の中で生活をスタートしました。しかし、最初の半年間は外食やコンビニ弁当に頼る生活で、食費だけで月4万円を超え、栄養不足による体調不良も頻発していました。このままでは学業にも支障をきたすと危機感を抱き、抜本的な生活改善に取り組むことを決意しました。
まず、家計簿アプリを導入して支出を詳細に記録し、無駄な出費を洗い出しました。次に、栄養学の基礎を独学で学び、必要な栄養素を効率的に摂取できる食材リストを作成しました。さらに、近隣5軒のスーパーマーケットの特売日や見切り品の傾向を調査し、最適な買い物ルートを確立しました。
特に工夫したのは、週末の作り置き料理システムです。日曜日に3時間かけて一週間分のおかずを調理し、冷凍保存することで平日の時間も確保できました。また、近所の農家から直接野菜を購入する仕組みを構築し、新鮮で安価な食材を安定調達できるようになりました。
この取り組みにより、月の食費を2万5千円まで削減しながら、定期健康診断では全項目で正常値を維持できました。また、浮いた費用で資格取得の勉強に投資することも可能になりました。この経験を通じて、限られたリソースを最大活用する計画力と、継続的な改善を実行する実行力を身につけました。

長所・短所の書き方
企業が長所・短所を質問する目的は、自己分析が適切にできているかを確認するためです。なかでも、重視されるのは、短所をどう認識し、どう改善しているかという点です。
基本は「長所は〇〇、短所は〇〇」と、これまでの項目と同じように結論から書くと読みやすくなります。加えて、長所・短所の内容が、自己PRと重複しないようにすることも重要です。
長所・短所の例文
一方で、私の短所は完璧主義的な傾向があることです。何事にも高い基準を設け、細部まで丁寧に取り組もうとするため、時として作業に時間をかけすぎてしまうことがあります。レポート作成では、参考文献を徹底的に調べ、何度も推敲を重ねるため、締切直前まで時間を要してしまうことがありました。現在は、作業開始時に全体のスケジュールを細かく設定し、各段階での完成度の目標を明確にすることで、効率的に高品質な成果物を作成できるよう改善に取り組んでいます。

良いESを書くために気を付けるポイント

良いESを書くためには、面接を見据えた工夫や自己分析の深さが求められます。
①面接時に話のネタになるものを含める
②アピールポイントとエピソードに関連性を持たせる
③具体的な自分の人柄をアピールする
④エピソードに面白みを持たせる
⑤しっかりと自己分析をする
⑥他人に添削してもらう
さっそく、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
①面接時に話のネタになるものを含める
ESは書類選考のためだけではなく、面接時の会話の土台にもなります。
そのため、エピソードの抽象度が高いと、面接官が深掘りしにくくなり、相手の印象に残りません。具体性のある話題や、話のフックとなる情報を盛り込むことが大切です。
例えば、人に驚かれた特技やユニークな経歴、マニアックでも良いので固有名詞を含んだ趣味や経験などを積極的に取り入れましょう。こうした話題はアイスブレイクのきっかけとなり、その後の面接を優位に進められます。
②アピールポイントとエピソードに関連性を持たせる
一貫性のないESは、採用担当者への説得力を失うため注意が必要です。
特に、アピールポイントとエピソードがずれていると、話がぼやけて印象が薄くなります。そのため、アピールポイントとエピソードには、必ず因果関係を持たせましょう。
全体のストーリーに一貫性を持たせることが、読みやすく魅力的なESにするコツのひとつです。
③具体的な自分の人柄をアピールする
ESで自分の人柄を伝えるときは、抽象的な表現を避けてください。
例えば、「私は責任感があります」だけでは伝わりません。どんな場面で、どのように責任感を示したかまで言及しましょう。行動や事実に基づいた具体的な描写を意識すると、人物像がはっきりしてきます。
④エピソードに面白みを持たせる
採用担当者の記憶に残るESには、個性や面白みがあるものです。
すべての項目を真面目に書きすぎると、内容がありきたりになり、全体の印象が薄れます。
また、有名人のエッセイなどを参考に、「日常のちょっとした面白さの切り取り方」を学ぶのもおすすめです。
⑤しっかりと自己分析をする
ESに書くことが見つからないと感じたら、自己分析が足りないサインかもしれません。
そこで、自己分析が足りないときには、「なぜなぜ分析」を試してみましょう。
企業が見たいのは、応募者の表面的な部分ではなく、もっと深くにある人間性や価値観です。自己分析により、採用担当者が求めているものを提示できるようにしましょう。
⑥他人に添削してもらう
ESの完成度を高めるには、客観的な視点での添削が欠かせません。
完成した直後のESには、思い込みや表現の甘さが含まれていることが多く、自分では気づきにくいものです。特に、書き上げた達成感から見直しが雑になることもあるため、第三者の目を通すことが重要です。

よくある質問

ESを書いていると、さまざまな疑問や不安が出てくるものです。ここでは、就活生からよく寄せられる質問に対して、実践的なアドバイスを紹介していきます。
最後まで諦めずに、納得のいくESを目指しましょう。
趣味・特技欄に何を書けばいいかわからない!
趣味や特技は、あなたの個性や熱量が最も伝わる項目です。しかし、ただ「好き」や「得意」と書くだけでは不十分です。
大したエピソードもなく自信がない!
そもそも印象的なエピソードをすぐに思いつく人は少数です。そこで大切になるのがエピソードの「どこに注目するか」です。
他人と被りそうなエピソードしかない!
似たエピソードを書いても問題はありません。大切なのは「表現の工夫」です。
添削してもらう相手がいない!
身近に添削してくれる人がいない場合は、AIツールの活用も有効です。

まとめ
ESの書き方と、採用されるポイントについて解説してきました。
ESの基本的な構成や書き方、注意点を理解することで、初歩的なミスを防ぎつつ、企業に伝わる内容が完成します。また、企業が重視する評価基準を知れば、より相手の期待に応えるESに仕上げられます。
各項目ごとの具体的な書き方や例文も参考にしながら、自分らしさをしっかりと伝えましょう。
最後に紹介した「良いESを書くために気をつけるポイント」も意識し、ぜひ採用担当者の印象に残る魅力的なESを目指してください。


