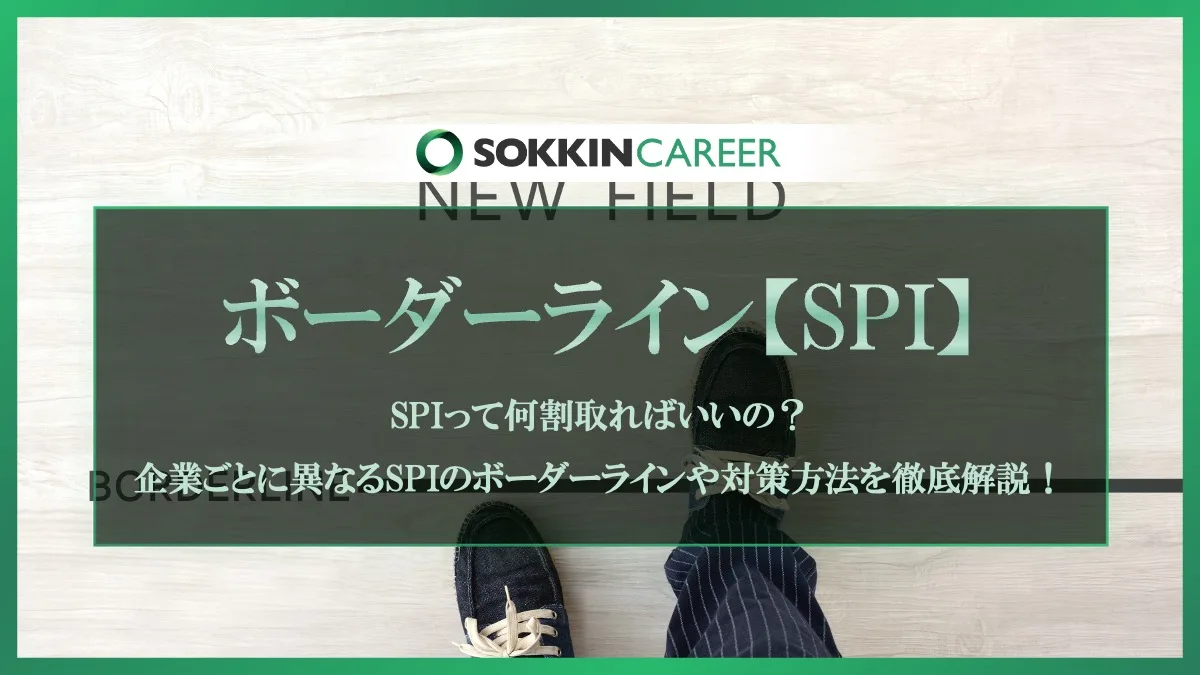SPI試験は、求職者の能力を客観的に評価するために、多くの企業が導入している指標です。
SPIのボーダーラインを下回ると面接に進めないケースも多いため、自分が志望する企業では何割取ればよいのか把握しておくことが大切です。
この記事では、SPIを突破して次の選考に進むには何割の正答率が必要なのか、企業ごとに異なるボーダーラインの目安を解説します。
SPIテストの対策方法や必要な勉強時間なども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
SPIテストのボーダーラインについて

まず、SPIテストの一般的なボーダーラインについて見ていきましょう。
以下でSPIから先の選考に進むために必要な点数と偏差値について解説します。
平均的なボーダーは?
そのため、平均的な6割〜7割という数字を最低限必要なものと意識して、それ以上の点数を目指して対策することが重要です。特に、大手の就職先や人気の会社を志望する人は早めに準備を始めて、しっかりとした学習をするようにしましょう。


点数よりも偏差値が重要
偏差値とは、自分の得点が受験者全体の中で相対的にどの位置なのかを示す数値のことです。自分が高得点を取れた場合でも、他の受験者も全体的に高得点ならば偏差値はそれほど高くなりません。逆に、自分が高得点を取れなかった場合でも、全体平均の点数がさらに低ければ偏差値は高くなり、次の選考に進める可能性が高まります。
企業別に見るボーダーライン

ここからは、企業別のボーダーラインについて解説します。
平均的なボーダーラインは6割〜7割ということをお伝えしましたが、実際の点数は企業によって異なります。7割程度が目安になるところもあれば、8割以上や9割以上が必要な会社もあります。
企業がSPIの点数に基準を設けるのは、応募者の基礎的な学力を測定し、足切りを行うためです。特に、応募者が多い人気の就職先では、全員に対して面接を実施することは難しいため、SPIの点数に一定の基準を設ける場合が多いです。まずSPIで足切りを行い、基準以上の点数を取った応募者のみ次の段階に進めるようになっています。
以下で業界や企業別に求められる割合の目安を紹介しますので、必要な点数を判断する際の参考にしてください。


求められる割合
以下の表は、SPIで求められる得点の割合をまとめたものです。
| SPI点数の目安 | 企業の例 |
| 90% | 日本銀行、外資系コンサル企業 |
| 80% | 住友商事、伊藤忠商事、三菱商事、丸紅、毎日新聞、産経新聞、朝日新聞、読売新聞、講談社、小学館、NHK、TBS、テレビ朝日、テレビ東京、共同通信、みずほ銀行、野村證券 |
| 70% | NTTデータ、NTT東日本、KDDI、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、ゆうちょ銀行、みずほ信託銀行、日本郵便、ANA、JR九州、味の素、サッポロ、シャープ、三井化学、三菱ケミカル、東京ガス、大阪ガス、中部電力 |
| 60% | 損保ジャパン、第一生命、中外製薬、住友生命、三井不動産レジデンシャル、竹中工務店、富士重工、ダイハツ、三井倉庫、大和証券 |
上記のように、基準が7割を超えるのは有名な大手企業が多くなります。一般的には6割〜7割程度が平均的な目安となるでしょう。8割以上の点数を取ることができればほとんどの企業で基準を超えることができます。
以下で求められる割合ごとにどんな業界の企業が多いのか具体的に解説します。
【6割】
求められる割合が6割程度の企業が特に多いのは、以下の業界です。
- 不動産業界
- 保険会社
6割という点数は、上記の業界に限らず全体の平均的な数字でもあります。努力さえすれば多くの人が取れる点数なので、早めに対策を始めて少しでも高得点を目指すようにしましょう。
【7割】
SPIで求められる割合が7割以上の企業が多いのは以下の業界です。
- 通信業界
- メガバンク
- インフラ業界
- エネルギー業界
7割というラインも、事前にしっかりと対策を行えば十分に合格可能な数字です。志望する業界や企業に関わらず、まずは7割以上を目標にして念入りに対策しておくとよいでしょう。
【8割】
目安として8割以上が基準となるのは以下の業界です。
- 総合商社
- 新聞社
- テレビ業界
- 大手銀行
総合商社やテレビ業界は、多くの人にとって憧れの就職先となるため、毎年応募者が殺到します。ライバルが多いことから足切りのために基準も高くなりやすいため、時間をかけて対策する必要があるでしょう。
【9割】
以下の就職先は、求められる割合として9割以上の得点が必要と言われています。
- 外資系のコンサル
- 日本銀行
特に外資系のコンサル企業は能力を重視する傾向があり、他の応募者のレベルも高いことから、求められる割合も高くなります。


SPIのボーダーラインを重視していないところもある
特に、独自の企業文化を持っているベンチャー企業や中小企業では、応募者の人柄や価値観、チームワークを見るために、面接やグループワークの評価を重視する場合があります。SPIの点数が低くても、面接で評価が高ければ内定をもらえる可能性は十分にあるでしょう。
テスト形式別にみるボーダーライン
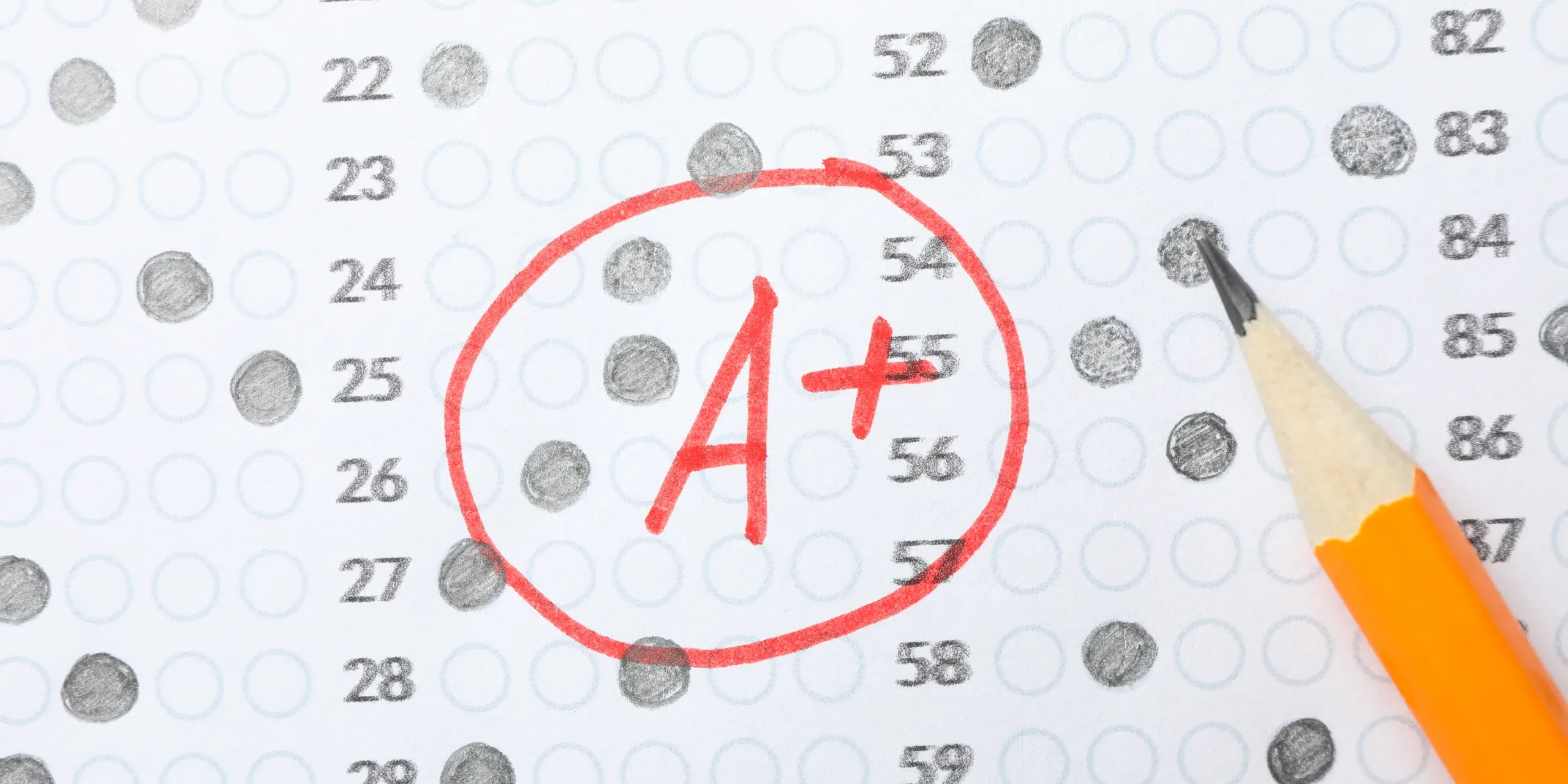
SPIの一般的なボーダーラインは6割〜7割程度ですが、テスト形式によっても異なります。
以下で3種類のテスト形式ごとに、一般的に必要となる点数の目安を解説します。
Webテスト
Webテストはパソコンとインターネット環境を使って自宅などからSPIを受験する形式です。コロナ禍の影響もあり増えている受験方法です。
Webテスト形式では、中学校・高校で学習したような基礎的な問題が多く出題される傾向があります。問題の難易度はあまり高くありませんが、忘れている内容が多くなるため事前の対策は必要です。
テストセンター
テストセンター形式は、専用の会場で受験する方式です。
テストセンター形式では、読解力などが問われる言語分野のテストと、数学的な思考が試される非言語分野のテスト、さらに英語分野に加えて構造的把握検査も行われることがあります。インターネットで受験する方式と比較して難易度は高めになり、基本的な学力だけでなく応用力を問われる問題も出題されます。
テストセンター形式で求められる点数の割合の目安は7割程度です。高い偏差値を取るために7割〜8割程度の得点を目指して対策を行いましょう。
ペーパーテスト
ペーパーテスト形式は、試験会場で紙ベースの試験を行う方式です。
問題の難しさはWebテスト形式に近く、中学・高校レベルの基礎的な問題が多く出題されます。また、ペーパーテスト形式は出題範囲が狭いため、事前の対策がしやすいという特徴があります。
SPIテストの対策方法

ここからは、SPIテストで高得点を取るための対策方法について見ていきましょう。
効果的な事前学習の方法に加えて、試験本番でのテクニックも解説しますので参考にしてください。
出題内容の把握
SPIの対策を始めたら、まずどんな問題をどのような形式で解くことになるのか、出題内容を把握しておきましょう。
出題される問題の傾向は毎回類似していますので、過去の傾向を知っておけば対策しやすくなり、本番でも落ち着いて対処できるようになります。
苦手分野の克服
出題内容が把握できたら、得意分野と苦手分野を判断して、自分が苦手とする分野を克服するための対策を行いましょう。
言語分野と非言語分野、英語分野の3つがありますので、まずは最も苦手な分野を重点的に学習するとよいでしょう。問題集を解き方が理解できるまで何度も繰り返し、苦手意識がなくなるようにしましょう。
時間配分を意識
SPI試験には制限時間があり、限られた時間内にできるだけ多く問題を解いて正解する必要があります。
事前に学習をしている段階で、試験を受ける本番での時間の使い方をイメージし、時間を計りながら問題を解くなどして慣れておきましょう。試験当日も、練習しておいた配分で時間の使い方を意識しながら問題を解いていくことが大切です。
模擬試験を受ける
本番に近い条件で模擬試験を受けておくことは非常に効果的な対策方法です。
まず、模擬試験の結果を分析することで、現時点で何割ぐらいの点数が取れるのか知ることができます。得意な分野と苦手な分野も分かってきますので、本番までに必要な対策も具体的になってくるでしょう。
試験当日に緊張や焦りで実力が出せないということがないように、時間を作って模擬試験を受けておくことが効果的な対策方法となります。


問題集を何周もする
SPIの問題集を活用して、過去問をできるだけ多く解いておくことも効果的な対策方法です。
SPIでは毎年似たような問題が出題されることが多いため、繰り返し過去問を解いておけばパターンに慣れることができます。同じ傾向の問題が出たときに対応しやすくなり、解答する時間も早くなります。
また、過去問で正解できなかった問題を分析すると、自分に足りない知識や苦手な分野が分かるようになります。解説をしっかりと読んで理解しておき、問題集をもう一周したときに正解できれば、実力が向上したことになります。
わからない問題は飛ばす
試験本番でのテクニックとして、時間管理のためにわからない問題を飛ばすのも重要なポイントです。
SPIは時間内にできるだけ多く正解することで高い得点を取ることができます。全問正解することを目指すのではなく、わからない問題や時間のかかる苦手な問題は思い切って飛ばして、得意な問題を素早くたくさん解くことが効果的です。
科目別の対策方法

ここからは、科目別の対策方法を見ていきましょう。
言語分野、非言語分野、英語分野で、それぞれどのような対策が効果的なのか解説します。
言語分野の対策方法
言語分野では論理的な思考力や文章の読解力を試す問題が出題されます。
特に、長文読解力や、空欄を適切な語句で埋める形式で出題される文章理解の問題が重要です。その他に、提示された二語の関係性を理解し、同様の関係を持つ語を選ぶ二語問題や、熟語の意味や構成を解答する問題もあり、語彙力も必要です。
また、言語分野でスコアアップを目指すには、長文問題で高得点を取ることが重要です。文章の主題や筆者が伝えたい主張を理解することを意識して、長文の読解力も強化しておくことも重要です。
その後、問題集や模擬試験を活用して、実戦形式で高得点が取れるか試してみましょう。
非言語分野の対策方法
非言語分野では数学的な能力と論理的な思考力が試されます。
まず、四則演算など基礎的な計算力を訓練して、素早く正確に解けるようになることが重要です。それに加えて、割合や比率、損益算、集合のほか、グラフや図表を扱う問題も出題されます。時間と距離、速度の関係を計算する速度算の問題も出題されますので、基礎的な物理の知識も必要です。
また、論理的な思考力を試す推論の問題も多数出題されますので、しっかりと対策を行いましょう。推論では、与えられた情報からパターンを導き出して論理的に結論を導く能力が求められます。問題集やSPI学習用のスマホアプリなどで様々な問題を解く練習をして慣れておきましょう。
英語分野の対策方法
英語分野は、主に英語の語彙力を試す問題と長文読解が出題されます。語彙力を強化しながら、英文を読むトレーニングをして少しずつ長文読解に慣れるようにしましょう。
語彙力を試す問題は、同意語や反意語を選択する問題や、英英辞典のように英単語の定義を適切に表す英文を選択する問題が出題されます。
読解力を試す問題は、英文の空欄を補う問題は文脈の理解力と語彙力の両方が必要です。長文読解は、複数の段落からなる文章を読んで、その内容についての設問に解答する形式です。
英語分野については参考書や学習アプリが多数ありますし、習得しておけばSPI以外でも役に立ちます。スキマ時間も活用して効率よく対策しましょう。
SPIで高得点をとれている時の確認方法

ここからは、SPIの試験を受けている最中に自分が高い点数を取れているのか確認する方法を解説します。
具体的には、出題された問題に多数正解している人にはより難しい問題が出題され、逆にあまり正解できていない人は、続けて出題される問題が簡単になっていく仕組みになっています。そのため、受験中に出てくる問題の傾向を見ることで、自分がどれぐらい点数を取れているのか予想することができます。
あくまで目安ですが、基本的には難しい問題が出ればでるほど、高い点数が取れていると予想することができます。逆に、簡単な問題ばかりが出ていると感じるときは、高い点数が取れていない可能性があります。
以下で、分野別にどのような傾向があれば自分の点数が高いと予想できるのか、その確認方法を紹介します。
言語分野の確認方法
言語分野で点数が高いときは、問題の種類として長文読解が出されやすくなるという特徴があります。
通常は長文読解は1問だけのことが多いです。しかし、点数が高い受験者には長文読解が2問〜3問出されることがあるようです。そのため、2問目の長文読解が出た場合は、これまでの問題で高い点数が取れている可能性があります。もし3問目の長文読解が出た場合はさらにその可能性が高いと言えるでしょう。
逆に点数が取れていないときは、長文読解よりも語彙の問題が出やすくなる傾向があるようです。
また、長文読解の問題のタイプとして以下の特徴があるときは、高い点数が取れている可能性が高いと思われます。
- 四角にチェックを入れる形式の問題が出される
- 文字数の制限がない文章抜き出し問題が出される
また、空欄補充問題の選択肢が文章抜き出しになっているものも難しい問題のひとつです。このタイプの問題には選択肢に文字数の指定があるものとないものがあります。このうち文字数の指定がないものが最も難しいため、この形式が出れば高い得点を取れている可能性が高まります。
非言語分野の確認方法
非言語分野で高い点数を取れているときの確認方法としては、推論の問題が出やすいという特徴があります。
推論の問題は、数字や図、文章の形式で与えられた情報から正しい選択肢を選ぶ問題です。計算問題よりも難しい問題が多いため、出題数の半分以上が推論の問題になっていれば高い点数が取れている場合が多いでしょう。具体的には、7問のうち4問、または8問のうち5問が推論になっていれば、それまでの問題で高い点数が取れていると予想できます。
また、それまで高い点数を取れているときは、推論の問題でも四角にチェックを入れるタイプの問題が出やすくなる傾向があるようです。これは言語分野の場合と同じですが、該当するものを全て選ぶ必要があるため難しい問題となります。
英語分野の確認方法
英語分野で高得点が取れているときは、長文読解問題が多くなります。特に、長文読解問題が4問出ているときは、高得点が取れている可能性が高いと言えるでしょう。


必要勉強時間について

すでに解説したように、SPIの対策は、出題範囲の把握、苦手分野の克服、問題集と模擬試験を計画的に進めるのが効果的です。特に、苦手分野の対策と問題集の繰り返しに時間をかけるとスコアアップにつながります。
もともとの知識量にもよりますが、ある程度学力に自信がある人でも、模擬試験も含めて合計30時間以上の時間を確保しておいた方がよいでしょう。
また、目標とする点数によっても必要な勉強時間は大きく変わります。一般的なボーダーラインと言われている7割以上を狙うとして、30時間以上の勉強時間が目安となります。
それ以上の高得点を目指す場合は勉強時間を長めに確保しておいた方が無難です。
- 8割を目標にするなら40時間以上
- 9割を目指すなら50時間以上
を目安に、しっかりと対策を行いましょう。
勉強を始めるタイミング

新卒の場合、試験を受けるのは3月後半から5月前半までの時期が一般的です。逆算すると、大学を卒業する前年度の12月ごろから勉強を始めるとよいでしょう。4年制大学の場合は、3年生の12月ごろが勉強開始の目安です。
上記で解説したように、勉強時間の目安は30時間〜50時間です。1日あたりどのくらいの時間をSPI対策に割けるかは人によって変わりますので、必ずしも12月を過ぎると遅すぎるというわけではありません。SPI対策以外のやるべきことも把握して、計画的なスケジュールを考えましょう。
ノー勉で行くとどうなる?

「SPIをノー勉で受けるとどうなるの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。就職活動ではSPI対策以外にもやるべきことはたくさんありますので、勉強の時間が確保できなかったり、間に合わないかもしれないというケースもあると思います。
以下で、対策なしでは厳しい理由を2つ解説します。
厳しい理由①
ノー勉では厳しい理由の1つめは、公式や単語など、知識が必要な問題が多く出るからです。
SPIは言語分野と非言語分野、英語分野がありますが、いずれも知識が必要な問題が多数出てきます。
たとえば、言語分野では単語の意味を知っていなければ正解できない問題が出題されます。非言語分野でも、計算を行うための公式を知っていないと正解できなかったり、時間がかかったりしてしまいます。
しかし、事前対策なしでは知識不足で正解できない問題が増えてくるので、ノー勉では厳しい場合が多くなるでしょう。
厳しい理由②
ノー勉では厳しい理由の2つめは、単語の意味や公式など必要な知識が、中学生から高校生レベルの内容だからです。
中学生・高校生レベルと聞くと簡単そうに感じるかもしれませんが、SPIを受けるのは高校を卒業してから何年も経過した後のことです。大学の授業で中学生・高校生レベルの復習をすることは基本的にはありませんので、忘れてしまっていることが多いでしょう。
まとめ
この記事では、SPIは何割取ればよいのか、企業ごとのボーダーラインや対策方法を解説しました。
ボーダーラインは企業ごとに異なるため、自分が志望する企業の目安を調べておくことが大切です。一般的には6割〜7割程度が多いため、8割以上取れれば多くの企業でボーダーラインを超えられる可能性が高まるでしょう。
SPI試験の対策方法としては、まず出題内容を把握して苦手分野の克服を目指し、過去問を解いたり模擬試験を受けたりする流れが効果的です。
ぜひこの記事でまとめたことを参考にしていただき、就職活動やSPI試験の対策で役立ててください。